みなさん、こんにちは。
今日は「強気」について見ていきます。これは嫌なことが起きたときに効果を大きく発揮するスキルなので、メンタルが弱い方やHSPの方(いわゆる、繊細さん)こそ身につけていただきたいスキルです。
イメージはサムネ画像の感じですね。
強気の解釈・姿勢
強気の解釈・姿勢は、ネガティブ思考により被害妄想をしそうになったときにこそ力を発揮するスキルです。こういう状況になったら強気の解釈・姿勢を意識してみましょう。例えば「それがどうした。そんなもん知るか!勝手に決めつけるな」と思うことで、被害妄想を吹き飛ばします。
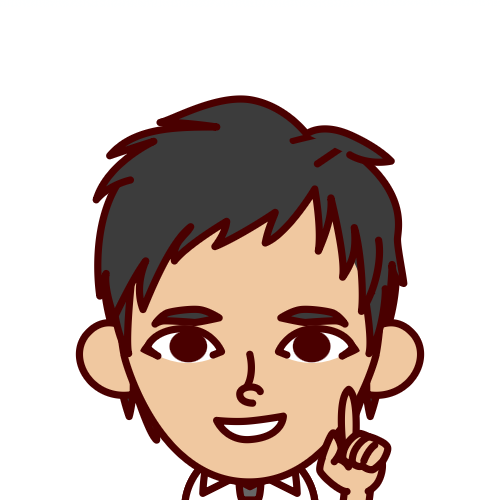
強気の解釈・姿勢は自信と関連性が高いものでもあります
キツいことを言われたら強気の態度に出てください。「だから何?」とか「それがどうした!」とか「そんなこと知るか!」という解釈でいきましょう。
あえて合わない人を切り捨てる勇気をもつ
強気の心(強気の解釈)を身につけるなら、あえて「こういう人はお断り、ノーサンキュー!」ということを宣言してみましょう。そして、そういう人がいたら「ゴミのように捨てる」イメージで距離を置いてみてください。最初は罪悪感を抱くかもしれませんが、徐々に慣れてきます。
僕は、ネガティブな人、マウントを取る人、感じの悪い人、謙虚さがない人、心理的安全性を確保できない方、権力を駆使して周囲を振り回す・マイルールを強要する人、怒りや脅迫で従わせる人、ハラスメント体質の方、承認欲求目的の自慢話ばかりする方(目立ちたがりの出しゃばり)、前に進もうとする人の足を引っ張ろうとする方とは距離を置いています。こういう人に対しては、僕は強気の姿勢で切り捨てています。「この人はない」と冷たく判断しています。
もちろん、自分のことを嫌っている人がいることもあるでしょう。そういう人がいたら放っておく、勝手にさせておきましょう。構うのではなく、強気に切り捨てましょう。
自分の悪口なら勝手に言わせておく。ネガティブな意見や批判は「数百人のうちのただの1人の意見にすぎない」と捉える。「ふーん、それで?」と適当に聞き流す。こういうことを少しずつやっていきましょう。
メンタルが弱い方、HSPの方への特別メニュー
特にメンタルが弱い方やHSPの方にとっては、強気の心(強気の解釈)はかなり抵抗があると思います。
本来なら、人間には冷たい側面、強気に突き放す側面があってもいいのです。相手は自分が思っているほど自分には興味がありません。現実から逃げるようなポジティブ思考をしたって相手は気にしません。強気の解釈をしていいし、適当力を使って妥協したっていいのです。
・・・・・・
これで納得して強気の解釈・姿勢ができるようになるなら、苦労はしないですよね。
そこで、メンタルが弱い方やHSPの方に向けた特別メニューをご用意いたしました。
いきなりはきついかもしれませんが、嫌な体験、ネガティブなことを言われた経験に対して、ここまで出てきた「強気・ポジティブ・楽しい」の3つの解釈をしてみましょう。
例えば怒られたときも、強気の解釈を使い「それはその人の意見。数百人いる知り合いの中のたった1人の意見にすぎない。反省すべきところだけ気を付ければ、引きずる必要はない」と捉えてみたらいかがですか?恥をかいたときも「それは長期的には何の影響もないし、この場にいる人以外は知らないからどうでもいい」と捉えてみてはどうでしょう?
また、上司や先輩から怒られたときも、そういう上司や先輩を「自分のメンタル力を上げてくれる講師・コーチ」と捉えましょう。そうすると自分の能力が上がることのワクワクも含めて「楽しい」解釈ができるようになります。
失敗をして大きく落ち込んでしまうこともあるでしょう。その場合でも、全く何もできなかったわけではありませんよね。1つや2つは良いことがあったと思います。それを全力でほめましょう。必ず「小さな1勝」の余地はあります。そうすればポジティブに解釈できます。
解釈の仕方を変えれば、過去の失敗だって変えられます。失敗をたくさん積んできた人のほうが成長できるし、経験に裏付けされたノウハウや自信もついてきます。だからこそ、強気に解釈していいのです。ポジティブに楽しく解釈してもいいのです。失敗を歓迎し、失敗をどんどん重ねることができる精神的余裕をもっていきましょう。
また、取り組む前についても「失敗して当たり前なんだし、とにかくやるだけだ!」と強気の解釈をしてみることで、目の前の出来事に大きく不安になってしまうことを防ぎやすくなります。
ちなみに、強気の姿勢を身につけるのに役立つ本があります。「一人反省会をして、いつも落ち込んでしまう人へ」という本がオススメですので、強気の姿勢を取り入れたい方はぜひ読んでみてください。
今回は強気の解釈・姿勢について見ていきました。強気の解釈・姿勢ができると嫌なことが起きたときでもすぐにメンタルを回復(復活)させることができ、診断士の仕事の効率低下を防ぐことができます。
次回からはいよいよ「謙虚さ」について入っていきます。
今回もありがとうございました。