みなさん、こんにちは。
早くも4連投です(笑)このままでいくと毎日書いていくのかもしれませんよ。
さて、今日は取材の学校の受講体験記②として、第1講から第4講までの内容や感想を書かせていただきます(第5講以降は明日の記事で書きます)。
それでは、よろしくお願いします。
取材の学校の講義時間
講座は最後の撮影班講義(オプション)を除いてすべてzoomで行われます。そして、講義時間は4時間です。1時間強が経つと5分くらいの休憩が入ります。
時間帯としては、9:00~13:00の午前の部と、14:00~18:00の午後の部があります。どちらも同じ内容なので、ご都合に合わせてどちらかに出ればOKです。また、第1講は午前の部、第2講は午後の部など、日程によって出る時間帯を変えてもOKです。ただし、一部の講義は人数の調整になるため、事前にどちらの部に出たいかのアンケート調査があります。
それから、8講のうち2~3回は午後の部の後にzoom交流会があります。それがある日は午後の部に参加する人が多い印象です(それ以外の日は午前の部に参加する人が多いです)。
第1講
テーマ:取材とは何か、質問手法等の基本
講師:姫野先生
最初の講義は取材の意義、取材に臨む姿勢や準備、質問方法、取材の流れについて学びます。取材の全体像を薄く広く見ていくイメージです。
と言っても、コミュニケーションのセミナーに近いので気楽に受けることができます。どちらかと言うとこの第1講は「受講生の緊張を取ること」が重視されています。
当たり前ですが、みなさん最初は緊張しています。zoom越しでも緊張感は伝わってきます。
そのため、今回の第1講だけでなく、前半の講義(第4講くらいまで)は講義のところどころでzoomのブレイクアウトルーム機能を使い2~3名でワークをする時間があります(部屋割りは事務局の方が行います)。
ここではなるべく多くの方と触れ合うことができるように事務局の方が人選を工夫してくれます。僕もここで多くの人と出会うことができ、取材の学校の同期はほとんどの方とFacebookの友達になりました。いかに多くの同期と人脈・ネットワークを築くことができるかは、後に獲得する案件の質や量にも関わってきます。
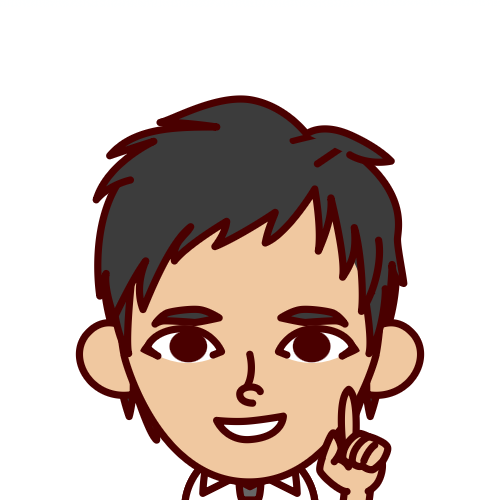
ここ、重要です!
また、緊張していることもあるので、この回は午後の部の講義後にzoom懇親会があります。ここは取材に関する内容でもいいですし、それ以外の話でも何でもできます。ここで緊張している受講生が一気に和やかになります。
ちなみに、僕は数年前に姫野先生の「メンタルビルディング」というセミナーに参加したことがあったため、元から姫野先生のことは知っていました。また、僕が先日まで担当していた「一発合格道場」の先輩だということも知っていました。なので、僕としては何の緊張もすることなくスムーズに取材の学校の講義に入ることができました。
よく考えると、それも良かったのかもしれません。そこで僕が緊張している他の受講生を和ませることができたため、多くの受講生とうまく話せてFacebookの友達にもスムーズになることができたと思います。
案件って本当に紹介してくれるの?
はい。紹介してくれます。
課題(3つ)の納期を守り、明らかにやっつけ仕事でやっていて文章がいい加減とかではないなら、きちんと案件は紹介されます。
あとはどれだけ積極的か、周りのメンバーと馴染んでいるかで案件の数は変わってきます。案件は個人ではなくチームで行います。そのため、コミュニケーション力の高い人のほうが様々な人とスムーズに調整ができますので、案件が回ってきやすくなります。
第2講
テーマ:インタビューの教科書
講師:原先生
事前に配布された「インタビューの教科書」の著者である原正紀先生の講義です。
第1講の内容を別の人が説明することでもう1回押さえるイメージです。これで取材の全体像を2回見たことになり、第1講のときよりも内容の理解は深まっていくようになっています。
この講義の前と後に「インタビューの教科書」をそれぞれ1回ずつ読んでおいたほうがいいかもしれません。講義は「インタビューの教科書」の重要な部分を深く掘り下げて解説する形になっています。
また、ここでもワークがあります。第1講で一緒にワークをした方とは別の方とワークをしていく可能性が高いです。こうすることによって、多くの受講仲間を作ることができます。
第3講
テーマ:人に読まれる記事を作るための座談会・執筆のポイント
講師:津田先生
はい、出ました僕の恩師、津田まどか先生!
僕と津田先生の出会いについては、こちらの記事をご覧ください。
講義はzoomで行うので、まどか先生もどこかからパソコンで参加しているのですが、後ろの背景を見てTAC名古屋校の教室からやっているとわかったときには驚きました(笑)
もちろん、まどか先生は僕が取材の学校に申し込んだことを知っていたため、zoom越しに僕を見つけたと思いますが、「サトシくんは私の教え子ですよ」などと特別視(えこひいき)することはありませんでした。この段階になると他の受講生も僕がまどか先生の教え子だということは知っていたこともあり、僕もどうやってまどか先生に声をかけたらいいかわからないまま、4時間の講義が終わりました。
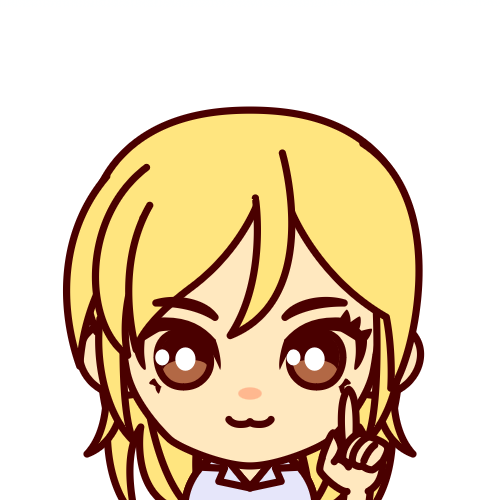
みなさんは私のことを「津田先生」ではなく「まどか先生」と呼んでね
さて、肝心な講義の中身はというと、取材の全体像のうち、ヒアリングの仕方や文章の書き方について掘り下げるイメージです。それに加え、オンライン取材のマナーやポイント、読者を惹きつけるタイトルの付け方、読みやすい文章の書き方などを教えてくれます。そして、メインの座談会は数人でグループになってワークを行う形となっています。
また、この回の後もzoom懇親会がありました。このあたりになるとほとんどの方がスムーズに話をできるようになりました。
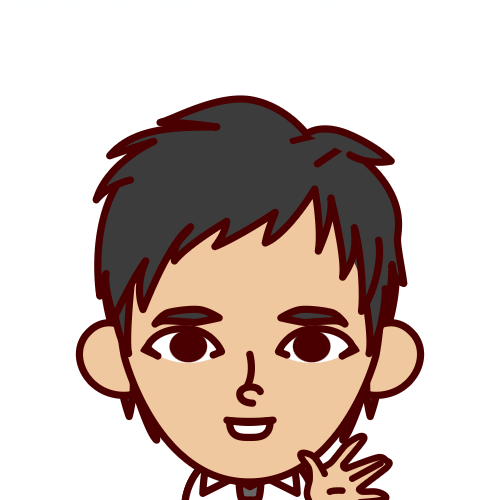
座談会とは、3~4人で特定のテーマについて話し合うものです。
その座談会の記事を書く案件も僕はいただきました。
その記事を書く際は第3講の内容を復習しました
第4講
テーマ:アウトプットの質を高める実践取材術
講師:富田先生・佐野先生
このあたりから内容が本格的になっていきます。徐々に「コミュニケーション方法」から「取材の方法」にウエイトがシフトしていきます。
取材の依頼状の書き方、取材の際のアイスブレイクのやり方、傾聴の仕方などを習います。
そして、重要なのが推敲・校正・校閲の方法(原稿に誤字脱字や文法的な間違い、不要なものがないかを探すイメージ)と、記事の構成の方法です。これを学べるのは本当に大きいです。
また、佐野先生はこの第4講の後にyoutubeで見る動画を配信してくれます。これはどのような書き方をすればいいのかを解説したもので、実際に記事を書く際の参考になります。いきなり「はい、では記事を書いてください」と言われても困ってしまいますからね。その見本を動画で見せてくれているイメージです。
ここまでが前半戦で、ここでGWが入るので1週間休みになります。
著作権講義
テーマ:執筆で注意したい著作権
講師:霜田先生
これは動画での講義になっています。第1講開始前から視聴でき、特定の期日までに視聴するようになっています。内容としては診断士の経営法務でやった著作権の内容の復習が半分くらいで、残り半分は実践的なものとなっています。
僕は第1講開始前に視聴しましたが、この第4講までで視聴していない場合は、GWの休みの間で視聴してしまうのがいいと思います。
さて、ここまでが前半戦でした。後半戦の体験記は明日公開いたします。お楽しみに!