みなさん、こんにちは。
もう5日連続ですか。日が経つのは早いですね(笑)
さて、今日は僕が言っていた取材の学校の体験記の第3弾として、第5講から第8講で行ったことと感想を書かせていただきます。
それでは、よろしくお願いします。
第5講
テーマ:ロールプレイング~やれば新たな気付きが見えてくる~
講師:姫野先生・米澤先生
この回はいつものように9:00~13:00、もしくは14:00~18:00ではなく、あらかじめ「あなたはこのグループなので、この時間に入ってください。何時から取材です」というように、グループと時間が決められています(事務局の方が指示をしてくれます)。なので、実は4時間ではなく、3時間弱で終わります。
全部で12のグループに分かれ、開始時間と終了時間がグループごとに異なります。しかし、3時間弱の時間配分についてはどのグループも共通です。①以下にある独立診断士に取材をして、②講師からフィードバックをもらい、③録音した音声の筆耕(文字起こし)をして、④各自で記事の構成を検討し、⑤気づきや反省点をグループのメンバー間で共有する、という流れになっています。
インタビュー相手(インタビュイー)の独立診断士は、荒井さん、山田さんの2人です。ただし、2人ともインタビューをするのではなく、インタビューをするのは荒井さんか山田さんのどちらかになります(どちらになるかは事務局の方が指定します)。そして、荒井さんのインタビューは姫野先生、山田さんのインタビューは米澤先生がチェックをしていて、インタビューが終わった後に講評をもらいます。
荒井さんか山田さんにインタビューをし、そのインタビュー内容をもとにした記事(800字)を課題として後で提出します。3つの課題のうち1つがここで出てきます。
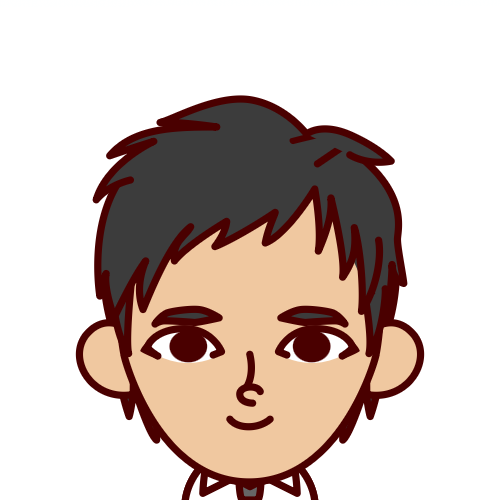
ちなみに、僕は荒井さんのインタビューで、姫野先生が講評をしてくれました
あらかじめ言っておきます。この回はほぼ確実にメンタルをくじかれます。へこみます。と言っても、独立診断士や先生から怒られるとかではなく、「自分のあまりの不甲斐なさに悔しくなる、落ち込む」というイメージです。
自分が思っているよりも、インタビューの質は低いものになります。思ったようなインタビューはできません。話し方がぎこちなくなったり、聞きたいことが聞けなかったり、事前に考えておいた質問項目ありきで質問して回答内容を掘り下げるような質問やとっさの質問が出なかったりします。時間オーバーとか逆に余ってしまうこともあるでしょう。
でもそれでいいんです。ここで失敗をすることで、後に案件をいただいて実際の記事を書く際のインタビューがスムーズにできるようになります。また、講師もそのレベルだということをわかった上で評価をしますし、できなかったからと言って後の案件獲得に支障が出ることはありません(みなさんうまくインタビューができないので)。
それから、姫野先生に続いて、インタビュー相手(インタビュイー)だった荒井さん、もう一人の先生の米澤先生も実は一発合格道場の先輩でした。講義の際はそれを知らなかったので、後で聞いて慌てて挨拶の連絡をしました。
なので、知らなかったとは言え、結果的には僕のインタビューは、インタビュアー、インタビュイー、講師の3人がすべて一発合格道場のメンバーだったことになります。ある意味で同窓会ですよね(笑)
第6講
テーマ:編集者・ライターの視点から見た取材
講師:馬渕編集長・川口先生
この回は4時間のうちに、①馬渕編集長の講義、②川口先生の講義、③馬渕編集長へのインタビューが行われます。具体的な時間配分は忘れてしまいましたが、メインは③馬渕編集長へのインタビューです。参加している受講生が1人2分(だったはず)を目途に馬渕編集長に質問をし、回答をもらいます。そして、このインタビュー(他人の質問・回答内容でもOK)をもとに課題(800字)を提出します。しかも、この馬渕編集長のインタビュー記事の出来によって、企業診断の案件に指名されるか、企画提案会に参加できるかが決まるので、結構重要です。
ただ、メンタル的なヤマは①馬渕編集長の講義に来ます。ここでは「プロとしての心構え」を紹介されます。甘い気持ちでやってもらっては困る、初歩的なミスをしたらプロとして失格など、厳しい言い方をしてきます(でもこれはわざとやっています。普段の馬渕編集長は謙虚な方です)。
人物や企業名の字を正確に書くことも強調しているので、馬渕編集長のインタビュー記事で馬渕編集長のところを「馬淵」と書いたらその時点でアウトと思っていいです。
第5講でメンタル的にやられているのに加え、ここでもちょっとピリッとするため、受講生のメンタルはどん底になります。そのため、この回の後はzoom懇親会があります。
懇親会ではみんな「馬渕編集長が言っていたあれって、本当なんですか?」と言って傷のなめ合いをしたり、「課題、どれくらいやっていますか?」と課題の進捗状況の探り合いをしたりします。ここで安心感を得ることでメンタルが回復します。
なお、メンタルはこの第6講が底なので、ここから先はどんどん上り調子になっていきます。
残りの②川口先生の講義もすごいです。川口先生はプロのライターなのですが、取材の際に実際に送った取材依頼書や具体的な記事を見せてくれます。もちろん、川口先生の取材のやり方(手順)についての説明もあります。
正直、企業秘密レベルのものが多いです。「ここまで見せてくれるの?」と言いたくなるほどですよ。
あれ?課題のもう1つはどこにいった?
受講生どうしの相互インタビュー(3人のチームになって三角方式でインタビューをしていき、1,500字×3記事を書く課題)は、講義内で扱うものではなく、受講生どうしで時間を取ってそれぞれインタビューを行います。
対面でのインタビューもできるように、チームのメンバーは地理的に近い人どうしになることが多いです。そのため、会議室やカフェなどでインタビューをしていた人もいました。僕はzoomでしたが、zoomでも40分あれば十分なインタビューができます。
なお、課題の提出は3つとも6月上旬になっています。日があるからまだやらなくていいやと思っていると、あっという間に納期近くになって慌ててやることになってしまうので、早いうちに仕上げてしまいましょう。
課題の提出期限に間に合わなかったらその時点で案件獲得はないと思っていいです。
また、提出期限ギリギリで慌ててやっつけ仕事でやるのもNGです。そういう記事は誤字脱字が多い、意味がわかりにくいなど文章の質が悪いため、案件獲得にはつながりません。
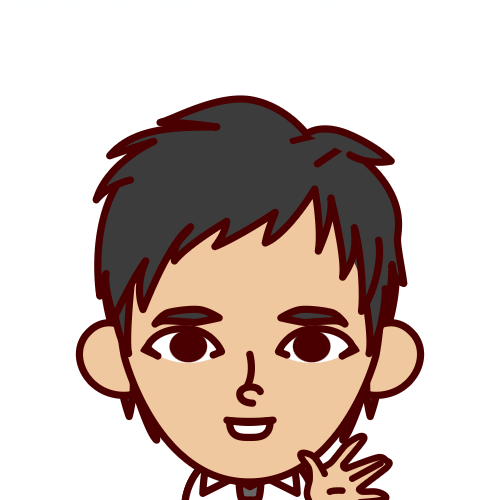
逆に言うと、やっつけ仕事でやらないで、きちんと提出期限に間に合えばいいのです。そのためにも、バッファとして2~3日の余裕日数をもっておくといいですよ。
第7講
テーマ:取材の写真撮影
講師:石田先生
第7講は写真撮影についての講義です。良い写真を撮影するための、撮影技術に関する知識、写真に関する知識、空気作りに関する知識を学んでいきます。ここではNG写真も学んでいき、実際に記事を書く際の写真にも活かされています。
つまり、写真の基本を学ぶものとなります。ただ、「基本」と言っても扱う内容は本格的です。構図やピントの合わせ方の他にも、「絞り」とか「シャッタースピード」などの専門用語も出てきます。
この石田先生は、第8講の後のオプション講義(参加は任意)も担当しています。僕はオプション講義には参加しなかったのですが、この第7講の内容の応用編・実践編です。そして、このオプション講義を履修し、オプション講義のテストに合格すると、「撮影班」のメンバーになることができます。
撮影班のメンバーになると、いただいた案件の取材の際に写真を撮影することができ、その写真を自分の記事で使用することができます(撮影班以外のメンバーは、一部例外はあるものの、インタビュー相手から提供してもらわないと写真を記事に掲載することができません)。
このあたりになると、3つの課題のことをどの受講生も気になっています。設定されたチームごと、もしくは個別に他の受講生に「あの課題、どこまでいきました?」とか「校正ってどうやってやりましたか?」などと連絡することが多くなります。
また、校正の依頼や修正稿、完成稿、写真のことなど、1日単位でスケジュールを気にするようになります。課題の提出期限(納期)は6月上旬なので、5月末から6月上旬は特にソワソワするような形になります。
そのため、受講生どうしで協力し合うことが多いです。ここで多くの方と仲良くなっている人のほうが協力を得やすいですので、zoom懇親会などに参加して多くの方と仲良くなっておきましょう。
なお、課題についての質問や相談があれば、事務局に連絡すれば丁寧に回答してくれます。僕は何回も事務局の方を頼りました。
第8講
テーマ:執筆プロジェクト事前説明会
ここは講師はおらず、事務局の方が説明してくれます。
「取材の学校ではこんな執筆案件を用意しています」という一覧を見せてくれて、それぞれの案件ごとにルールや報酬などの説明をしてくれます。
この説明をもとに、6月と9月に執筆案件のアンケートが行われます。ここで第1希望から第5希望まで回答し、集めた回答から事務局の方が各受講生に案件の紹介をします。基本的には1~3つの案件を得ることができます。
また、この第8講の数日後に、馬渕編集長への企画提案会に招待されるメンバーも発表されます。この企画提案会は馬渕編集長に認められた人(第6講でやった馬渕編集長へのインタビュー記事の課題がある程度以上の出来である人)しか参加できません。と言っても、課題の評価が超優秀な選りすぐりのメンバーというイメージではなく、課題の評価が「不可」以外の人は参加できるイメージです。なので、思ったよりも参加者は多いです。
企画提案会に招待された人は、最大2つまで企画を提案することができます。パワポのフォーマットに企画内容を書いて事務局に提出します。そして、企画提案会のときにその企画内容を馬渕編集長にプレゼンして、「採用」、「もう1回練り直しての再提出」、「不採用」の3つのジャッジがされます。基本的には「採用」と「再提出」の企画が採用され、実際に企業診断などの記事を執筆することができます。僕なら「メンタル弱め受験生のためのモチベーション向上法」と「独特経営の社長インタビュー」の2つの企画を提案し、2つとも採用され、それぞれインタビューをして記事を執筆し、企業診断に掲載されます。
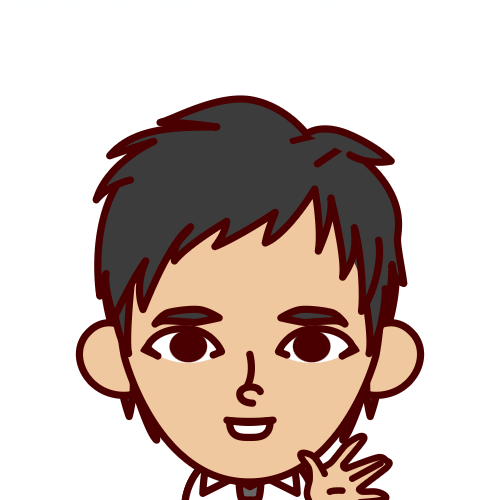
記事を書くと個人名刺に診断士活動内容として書くことができ、大きなアピールができます
特別講義(オプション)
ここでは取材の学校の主宰の堀切さん、事務局長、事務局の方(毎年異なります)と、ここまでの講義で出てくれた一部の講師の方が、診断士として活躍するための秘訣を紹介してくれます。結構なぶっちゃけ話も出てきます。なお、普段の講義はzoomで録画されるのですが、この特別講義だけはぶっちゃけ話が出てくる関係で、録画なしになります。
この回はオプションなので参加は任意ですが、録画はされないということで、時間があればぜひ参加していただきたいと思います。
ここまでが取材の学校のカリキュラムとなります。次回はカリキュラム修了後、実際にもらえる執筆案件についての体験記をご紹介します。