みなさん、こんにちは。
前回はビジネスモデルとドメインの違いについて見ていきましたが、今回はドメインの具体的な設定方法について見ていきます。
それでは、今回もよろしくお願いします。
今回も眠くなりそうなので、うるさい気動車をサムネ画像にしました。この車両は元は特急車両でしたが、改造されて普通列車として松山~宇和島の区間で運転されています。
ドメインの設定手順
こちらも前回と同じくチャットGPT先生による見解をお伝えします。
自分(または自社)のビジネスドメインを設定(定義)する方法は、大きく分けて以下のステップで考えると明確になります。
ステップ1:「誰に」「何を」「どうやって」を整理する
これは、エーベルの3次元モデル(顧客・ニーズ・技術)を活用するものです。
前回の復習ですが、ドメインを設定(定義)する上で考える必要があるのは以下の3つです。
- 誰にサービスを提供したいですか?(顧客層:誰に)
- その人たちは何に困っていますか?(ニーズ:何を)
- あなたはどんな強み・方法で応えられますか?(手段:どのように)
このモデルの最大の特徴は、「どんな顧客に対し、どんな機能を、どのような技術によって提供していくのか」という顧客との接点にフォーカスしている点にあります。
つまり、「コアターゲットは誰で、そのターゲットの望む価値は何か、そしてその価値を提供するための技術は何か」という順で定義していくことが重要である、という考え方です。
- 誰に(=顧客)
• 自分のビジネスが価値を提供したい相手は誰か?
• 例:ビジネスマン、子育て世代、中小企業、地方の高齢者 など - 何を(=ニーズ・課題)
• その顧客が求めているもの・困っていることは何か?
• 例:効率化したい、安心したい、かっこよく見せたい、時間がない など - どのように(=自分の強み・手段)
• そのニーズに対して、自分はどんな手段・技術・ノウハウで応えるのか?
• 例:アプリ開発、動画制作、商品開発力、接客力、地域ネットワーク など
ステップ2:文章で「ドメイン」を定義する
上記をもとに、次のような形で言語化します。要はステップ1の内容を文字化するだけです。
「〇〇な人々に、△△という価値を、□□という手段で提供するビジネス領域」
例1:個人デザイナーの場合
「地方で活動する中小企業に、ブランド力を高めるロゴとデザインを、ヒアリング重視のデザイン制作を通じて提供する領域」
例2:オンライン英会話サービス
「英語に苦手意識を持つ社会人に、実践的で話せる英語力を、AIと外国人講師による会話シミュレーションで提供する領域」
参考:さらに深めたい人向けの補助ツール
• SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)で自分の立ち位置を整理
• バリュープロポジションキャンバスで、顧客ニーズとの一致度を分析
• ポジショニングマップで競合との差別化を可視化
このあたりは診断士ならお得意ですよね。3C分析やPEST分析、バリューチェーン分析も役に立ちます。
物理的定義と機能的定義
ドメインといえば、診断士の企業経営理論で物理的定義と機能的定義を習いましたね。どちらが具体的で、どちらが抽象的か覚えていらっしゃいますか?
せっかくなので、復習がてら見ていきましょう。
物理的定義
ドメインの物理的定義とは、事業領域を製品やサービス、技術といった物理的な側面から定義する方法です。
具体的には、企業が提供する製品やサービスの具体的な実態に着目し、事業領域を明確にする際に用いられます。
例:
自動車メーカーであれば「自動車」、映画会社であれば「映画」、鉄道会社であれば「鉄道」。
物理的定義は、物理的定義は、製品(サービス)中心の考え方で、製品やサービスそのもの、つまり「モノ」を基準にドメインを定義します。例えば、鉄道会社が「鉄道」という製品を基準にドメインを定義する、といった具合です。
物理的定義はドメインの定義として最も簡単な方法で、物理的な要素に焦点を当てるため、事業領域を明確にすることができます。しかし、製品やサービスが陳腐化することによって、ドメインが狭まってしまうリスクがあります。また、事業の将来的な成長の方向性を見出すのが難しい場合があります。つまり、物理的定義は事業活動の展開範囲が狭くなり、現在の事業領域を超える発想が出にくいデメリットがあります。
機能的定義
ドメインの機能的定義とは、企業や組織が提供する製品やサービスが、顧客にどのような価値や機能を提供するか、という視点からドメインを定義する方法です。
つまり、顧客のニーズや、企業が提供する「機能」を軸に、その事業領域を規定します。
例
鉄道会社であれば、「輸送」をドメインとして定義する。
映画会社であれば、「エンターテイメント」をドメインとして定義する。
病院であれば、「医療」をドメインとして定義する。
機能的定義は、機能的定義は顧客中心の考え方で、製品やサービスが提供する「機能」や「価値」を重視するため、より幅広い事業展開や顧客ニーズへの対応が可能になります。
顧客のニーズや提供する機能にフォーカスすることで、将来の事業展開や事業拡大を容易に検討できます。つまり、機能的な側面からドメインを定義することで、新たな事業の可能性を広げることができます。
また、製品やサービスそのものよりも、顧客が求める「機能」を重視することで、技術革新や市場の変化に対応しやすくなります。
ここで、物理的定義を行ってしまうと、日々環境が変化する現代においては時代とともにいずれ陳腐化する危険性があります。
また、物理的定義により企業ドメイン・事業ドメインを狭めてしまう過ちをマーケティング近視眼(マーケティング・マイオピア)と言います。
そのため、物理的側面よりも機能的側面からドメイン定義するほうがいいとされています。
機能的定義は自分が提供する商品やサービスが実現する機能に着目した定義であり、物理的定義よりも適切な範囲をドメイン領域として定めることができ、将来における事業拡大にも適応しやすいとされています。
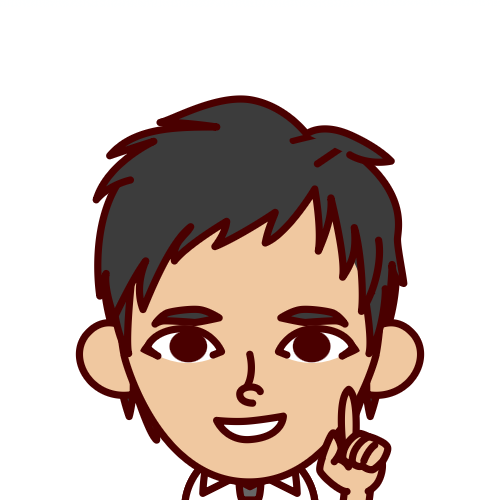
なお、物理的定義から機能的定義に切り替えることを「ドメインシフト」と言います
ただし、機能的定義はドメインが抽象的になりやすく、経営資源が分散しやすいデメリットがあります。
企業ドメインと事業ドメイン
ドメインにはもう1つ切り口がありましたね。企業ドメインと事業ドメインです。1次試験の企業経営理論では頻出のテーマですね。
こちらの違いについても復習していきましょう。
企業ドメインと事業ドメインは、焦点を当てている範囲が異なります。
企業ドメイン
企業ドメインは、企業全体がどのような領域・社会的役割で存在するかを示すもので、企業が定めた自社の活動範囲や競争領域のことを言います。
特徴としては、以下のことが挙げられます。
・企業の存在意義やミッションに関わる。
・長期的・抽象的な概念
・全体戦略やブランドイメージに影響する。
例
「人々の健康を支えることを使命とする企業」→ 製薬、食品、フィットネスなど複数の事業を含む可能性がある。
企業ドメインは企業理念やビジョン、自社の強み、市場ニーズなどに応じて定義され、定めた活動範囲に対して経営資源の集中投下が行われます。企業ドメインの定義は、自社の存続や成長に多大な影響を与える、とても重要なファクターだと言えます。
企業ドメインは経営理念・ミッションとつながっています。
事業ドメイン
事業ドメインは、企業が定めた自社事業の活動範囲や競争領域のことで、企業が展開する具体的な事業の範囲やターゲット市場を指します。ビジネスモデルとつながるのはこちらです。
特徴は以下のとおりです。
・個々の事業ユニットに着目。
・より具体的・実務的な内容。
・製品・サービス、ターゲット顧客、競合などを明確にする ←エーベルの3次元定義のことです
例
「高齢者向け健康食品の販売」→ 特定の製品・市場にフォーカスしている。
企業ドメインが企業全体の活動領域を定義するものに対し、事業ドメインは事業の活動領域を定義するものとなり、企業ドメインは事業ドメインの上位概念となります。
事業ドメインが定義されることで、競合他社が明確化され、業界における自社事業の課題も明確化されてきます。これにより、いつ、どのように経営資源を投下していくかを企画し実行していくための計画ができるようになります。
ドメイン設定の留意点
ドメインには適切な広さがあります。
広すぎると経営資源が分散し管理が難しくなりますし、競争にも巻き込まれやすくなります。
一方、狭すぎると顧客に認知されにくくなりますし、成長を限定してしまう可能性が生じます。
このことからドメインを設定する際は、将来、自社が向かう方向性や、現在保有している経営資源及び外部資源の活用を念頭に、自社の強みを最大限に発揮できる活動領域を注意深く見定め、広すぎず狭すぎない企業・事業ドメインを決定する必要があります。
今回はドメインに関する内容を見ていきました。
前回と今回は教科書的なことの記事になってしまいましたが、次回からは具体的に僕のキャリア分析の内容をお送りします。
今回もありがとうございました。