みなさん、こんにちは。
今回は重要性が高い記事です。
内容としては、相手の警戒心を取ることに近いものです。
それでは、よろしくお願いします。
相手に安心感、心理的安全性、信頼を与える
相手と初めて接するとき、大事なものがあります。それが相手に安心感や心理的安全性、信頼を与えることです。
つまり、接して与える三大要素とは、安心感、心理的安全性、信頼の3つです。
活躍する診断士の三大態度みたいにまた3つです(笑)
心理的安全性とは、組織の中で自分の意見や気持ちを安心して発言できる状態のことです。具体的には、上司や同僚に異なる意見を言っても、人間関係が壊れたり、拒絶されたりしないとメンバーが確信している状態を指します。メンバーが互いにリスペクトし合い、安心して自己開示や貢献ができるなら、心理的安全性が確保されていると言えます。
相手に安心感や心理的安全性、信頼を与えることにより、相手は心を開いてくれます。これは日常的な会話でも、コンサルティングや伴走支援でも同じです。どれも「人間を相手にしている」ということでは同じですからね。人間がコミュニケーションを図るに当たって安心感、心理的安全性、信頼を求めている以上、仕事だろうがプライベートだろうが同じなのです。
みなさんの周りにも、なぜかあの人だけには話しかけてくれる、あの人は周りの人とよく話しているという人がいますよね。
例えば、シャイな人でも話せるようになるのは、この3つの要素を満たしているからです。
相手の警戒心を取る
以前の「相手の警戒心を取る」の記事でも、シャイな方も話しかけることができる「特定の人」というのを見ていきました。こういう人は心のコップを上に向けることがうまいということでしたね。まさにこれは話す・聴くことによって相手に安心感、心理的安全性、信頼を与えているのです。
うまく話しかけたり、アイスブレイクで共通項を見つけ出したり、聴いているときは口角や眉を上げたりすることで、相手の警戒心を解いて、安心感、心理的安全性、信頼の三大要素を与え、心のコップを上に向かせることができます。
また、この三大要素があると、発言や行動も相手が自分からやるようになり、パフォーマンスが向上します。
こういうところからコミュニケーション力の差がつき、人脈・ネットワークや仕事の獲得に差がついてくると思います。そのため、僕は初めて会った人との会話は特にこの3要素を与えることを重視しています。
もちろん、「ポジティブ・楽しい・謙虚」の三大態度と相手への敬意なども意識しながら話しています。
僕がほめ達のスキルを使って相手をほめること(話を聴く、挨拶することも)はもちろん、キューピット的な役割をすることも、緊張している相手に安心感や心理的安全性、信頼を与えるためです。
三大要素の留意点
この三大要素にも留意点があります。
①感情任せの八つ当たりをしたら終わり
一度でも理不尽な指摘や感情任せの八つ当たりをしたら心理的安全性はなくなります。心理的安全性がなくなると、そこから信頼や安心感もなくなります。そして、縁を切られるか、切らなくても距離を置かれて最低限の会話しかしなくなります。
僕もある人から感情任せの八つ当たりをされたことがありました。それまで数年来の付き合いで信頼していましたが、それによってその人への心理的安全性は一気に崩れました。もちろん安心感も信頼もなくなりました。いつまた感情任せの八つ当たりをされるかわからないですから、しばらくは関わることもやめました。
一応、あとで「あの時は仕事が忙しくて精神的にキツかった」と言ってきましたが、もう遅いです。今は距離を置いて最低限の会話をしていますが、近いうちに縁を切ると思います(他の人からもそのほうがいいと言われていますので)。
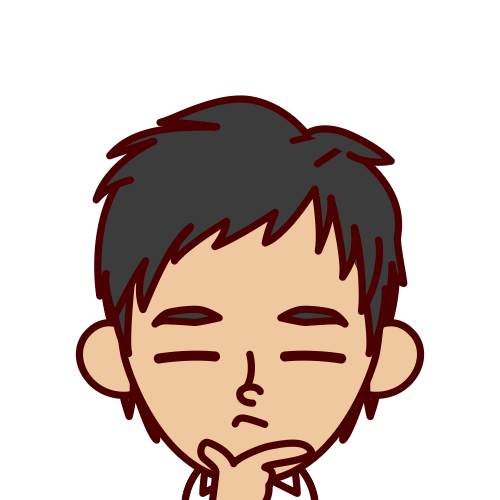
この「いつまた感情任せの八つ当たりをされるかわからない」と警戒されることが痛いです。心理的安全性がなくなるとこの警戒が取れません
えー、それだと良いこと以外何も言えなくなるじゃん!
と思ったみなさん、ご安心ください。
この三大要素、つまり相手に安心感や心理的安全性、信頼を与えることができれば指摘などしてもOKです(ただし理不尽な指摘や感情任せの八つ当たりはNGです)。
相手に安心感や心理的安全性、信頼を与えることができてはじめて、ほめるだけでなく改善点を指摘してもOKとなります。
逆に言うと指摘をして相手を不満にさせた場合、それは相手に安心感や心理的安全性、信頼を与えていないからです。打ち合わせとか、会社の上司・部下の会話でよくありますよね。例えば打ち合わせで口論や誰かを責める内容が出てきたとしたら、そのメンバー間で安心感、心理的安全性、信頼がまだ構築されていないと思われます。
具体的な指摘の仕方は「注意する、叱ることもある」の記事をご覧ください。
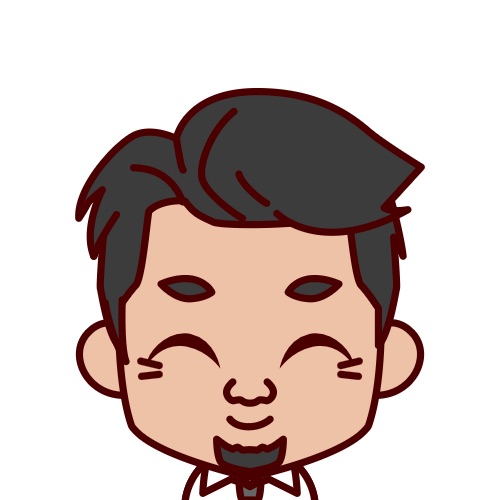
「ほめる→指摘→ほめる」のサンドイッチで、ほめることを8割、指摘を2割くらいの割合でやることがコツです
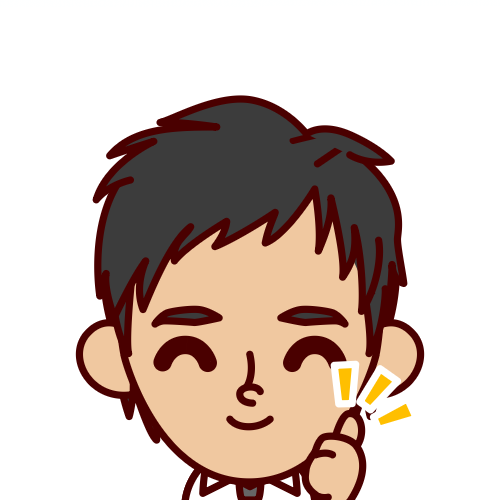
指摘の前に「惜しいのは」とか「強いて言えば」、「欲を言えば」をつけるといいですよ
僕は、打ち合わせは肯定的に行うものだと考えています。ポジティブな発言はもちろん、感謝や尊重もする打ち合わせこそが、効率的で生産的な打ち合わせだと思います。
先輩や上司として後輩や部下に指摘をする場合、相手に対して成長や改善の期待を込めていること(相手の成長や改善の可能性を承認すること)、自尊心やプライドを傷つけないことが求められます。これがない状態で指摘をすると、心理的安全性や安心感・信頼がなくなり、心を閉ざしてしまいます
②疎外感が出ると心理的安全性が崩れる
一度心理的安全性を構築し、安心感や信頼を得た人でも、話しかけてもらえない、特定のグループができてしまったなどにより、どこかのタイミングで疎外感を感じてしまうことがあります。その段階で心理的安全性がなくなります。つまり安心感や信頼もなくなります。
「特定のメンバーどうしでつるまない」の記事でも見たように、特定のグループだけでつるんでタメ口での会話や内輪ノリが目立ってしまうと、グループの外にいる人はアウェー感・疎外感を抱きます。そうなるとその特定のグループのメンバーはもちろん、コミュニティ自体に対しても、他のメンバーに対しても心理的安全性がなくなります。そして安心感や信頼もなくなり、コミュニティから去っていきます。
こういうことは相手は指摘してくれません。黙って離れていくだけです。だからこそ、本人が入りたくない意思表示をしていないなら、特定のメンバーだけで固まってしまって誰かを仲間外れにすることは避けたほうがいいです。置いてきぼりになっている人はいないかを意識し、いたら声をかけることが重要です。
このあたりのスキルはHSP(いわゆる、繊細さん)の人は得意です。
今回は重要な記事として、接して与える三大要素を見ていきました。
今後も活躍する診断士の三大態度(+相手への敬意など)と共によく出てくると思います。
今回もありがとうございました。