みなさん、こんにちは。
今回はキャリア分析とは関係なさそうなタイトルですが、バッチリ関係しています。
具体的には、前回の記事で出した「C.コミュニケーション系」の話ですね。特に双方向コミュ力に関連する話です。前回、双方向コミュ力だけはレッドオーシャンの強みだけど今後のキャリアの路線のためには必要になると述べさせていただきましたが、その理由が今回見ていくものです。
また、路線としては講師とコンサルティングの路線の話(執筆にはあまり関係ない話)になります。
それでは、今回もよろしくお願いします。
今回のサムネ画像は、アンパンマン列車です。アンパンマン列車はJR四国の様々な区間の特急に導入されていて、今回の四国キャリア分析合宿でもよく見かけました。今回の画像は松山~宇和島の特急宇和海に導入されているアンパンマン列車です。
何でも話せる、相談できる雰囲気は重要
この「何でも話せる、何でも相談できる雰囲気」がないと、診断士としての仕事、特にコンサルティング(伴走支援)はうまくいきません。つまり、僕の今後のキャリアの路線がうまくいかなくなります。
ここまでの僕のブログを見ていただいている方なら耳にタコかもしれませんが、診断士の三大態度は診断士の仕事には絶対に必要になります。
例えば上から目線でネガティブなことばかり言う診断士や、グチばかりでつまらなそうな診断士だと相手も満足しませんよね。
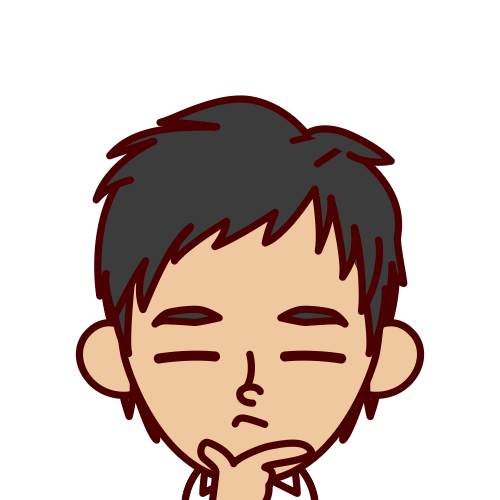
でも診断士の中にたまにこういう人っていますよね。プライドが高い人にありがちです
この三大態度がある人なら心理的安全性を確保できますから、安心できますし、信頼もできます。
安心感、心理的安全性、信頼については「接して与える三大要素」です。これについては先日詳しく解説しています。
この「心理的安全性」が確保できないと、今回のタイトルである「何でも話せる、何でも相談できる」ができないんですよね。
例えば「この人はいつダメ出しをするかわからない」という人だと、本音を言うことや込み入った相談などはしにくくなります。
特にメンタルが弱い方やHSPの方(いわゆる繊細さん)だと、一度でもダメ出しをしたら心理的安全性は確保できなくなります。
これは診断士でも同様です。相手企業の社長や従業員も人間ですから、心理的安全性があるかどうかで話せる内容も変わってきます。ネガティブな回答が返ってきそうな診断士やダメ出しをしてくるような診断士だと心を開いてくれないから、本音や込み入った話などは出てきません。
そうなるとコンサルティング(伴走支援)は表面上の浅い話しかできなくなるので、解決に必要な材料が揃わず、解決策も不十分なものになり、コンサルティング(伴走支援)は失敗します。
結果、先ほど見たような上から目線でネガティブなことばかり言う診断士や、グチばかりでつまらなそうな診断士がたくさん出てきてしまうのです。
自分の態度の悪さが原因なのに、相手企業の社長や従業員のせいにするのは診断士に限らず税理士のコンサルティングでもよく見られ、いわゆる「士業あるある」となっています。
逆に心理的安全性がある診断士なら相手企業の社長や従業員も心を開いてくれます。そうなれば本音や込み入った話も出てくるので、コンサルティング(伴走支援)は深いレベルまで進み、解決に必要な材料が揃い、解決策も十分なものになり、コンサルティング(伴走支援)はうまくいくという流れになります。
人間性が結果につながる
ここまでの内容の言い方を変えると、知識やノウハウはすごいけど人間性が悪ければ契約には至らないし、続かないことになります。こういう人は「何でも話せる、何でも相談できる雰囲気」はありませんからね。
「ポジティブ、楽しい、謙虚」の三大態度の他にも、例えば熱量が多くリアクションが大きい人のほうが人間性が良いように思われ、相手から好まれます。そうなると何でも話せる、何でも相談できる雰囲気が出てきます。
また、うまくいかないときに言い訳をしない責任者意識や素直さも人間性に反映されます。
仕事のときは承認欲求は封印する
これは三大態度のうちの「謙虚」に該当するものです。
自慢話ばかりする人だと「何でも話せる、何でも相談できる雰囲気」はないですよね。
コンサルティングを含め仕事のときには承認欲求は持ち出さないことが重要です。自慢話をしてくる診断士なんて、相手企業の社長や従業員からしたらウザいだけです。承認欲求を持ち出さないためには精神的・時間的余裕が必要で、そのためには自己肯定感の高さが必要です。だからこそメンタルを向上・矯正させる必要があるのです。
結局のところ、活躍する診断士に必要な三大態度(+相手への敬意など、素直)、接して与える三大要素が必要になります。
「先生」ではなく「伴走者」として接する
これはコンサルティングはもちろん、講師業でも同様です。受講者の相談対応の際に一方向のコミュニケーションだと今は時代遅れです。
双方向のコミュニケーションや伴走支援をするなら、診断士は「教えてくれる」よりも「歩調を合わせて支援してくれる」が求められます。このほうが「何でも話せる、何でも相談できる」になりますよね。
「先生」だとどうしても「生徒、受講生」のように捉えてしまい、上から目線でのアドバイスをしたくなってしまいます。そうなると謙虚さがなくなりやすいです。
また、「先生の意見」と「社長がこれまで培ってきた経験からの考え」は需要と供給のベクトルが合わないので、双方向のコミュニケーションや伴走は絶対にできません。
診断士は先生であって先生ではない
確かに、診断士は「先生」と言われることがあります。僕も講師や執筆、コンサルティングでそのように言われたことはあります。しかし、相手はそう呼ぶかもしれないけど、自身は「先生」と思わないようにしています。
ベクトルを合わせる
ベクトルを合わせることも、双方向のコミュニケーションにとって重要なことになります。
つまり、診断士は相手企業の社長や従業員の考えに合わせる必要があります。診断士は供給側、相手企業の社長や従業員は需要側と例えるなら、この「需要」のベクトルやスピードはころころ変わります。それらに応じて供給のベクトルやスピードも合わせる必要があります。これが「双方向のコミュニケーション」の真髄です。そしてこれができる人こそ、相手企業の社長や従業員から「何でも話せる、何でも相談できる」と思ってもらえるのです。
今回は診断士のキャリアの路線に必要になってくる「双方向のコミュニケーション」について、「何でも話せる、何でも相談できる雰囲気」という観点から見ていきました。
今回もありがとうございました。