みなさん、こんにちは。
みなさん、こんにちは。
今回からビジネスモデルを見ていきます。
先日のドメイン系のところまでは曖昧に「講師」とか「ほめるコンサルティング」だけでしたが、ここらへんから「誰に、何を、どのように」など、具体的になっていきますよ。
と言っても、今回はどちらかと言うと教科書的な内容です。
それでは、今回もよろしくお願いします。
今回のサムネ画像は、アンパンマン列車の特急しおかぜです。これもよく考えたら「幼稚園児くらいの年齢の子供がいる親子連れに、アンパンマン列車を、指定席にアンパンマンシートを用意して運転する」というように、ビジネスモデルがしっかりとできています。
ビジネスモデルとは
ビジネスモデルとは企業がどのようにして価値を創造し、提供し、そして収益を得るのかを示す「仕組み」や「構造」のことです。
簡単に言えば、
「誰に、何を、どのように提供して、どうやってお金を稼ぐのか」を体系的に表したものです。
ビジネスモデルとドメインの関係
ドメインの記事でも見たように、事業ドメインがビジネスモデルにつながります。
ビジネスにおける「ドメイン」とは、企業が活動する事業領域やフィールドを指します。事業ドメインが個別の事業の活動範囲を定義するのに対し、ビジネスモデルはそこから「誰に」「何を」「どうやって」提供して収益を得るかという、事業の具体的な構造と収益獲得の仕組みを指します。
そして、事業ドメインのビジネスモデルは、企業が持続的な成長のために「誰に(顧客)」「何を(製品・サービス)」「どのように(提供方法)」提供するのかを定義し、競争領域を明確にすることで、経営資源を集中させ、競争優位を築くための企業活動の指針とする戦略です。
事業ドメイン
個別の事業の活動範囲や、企業が戦う具体的な領域を指します。企業ドメインの下位概念にあたります。
具体的には、エーベルの3次元枠組み(市場・顧客、企業が果たすべき機能、企業が持つ技術・能力)で具体化されます。
ビジネスモデル(事業の仕組み)
事業活動によって「付加価値」を「誰に」「何を」「どうやって」提供し、そこから「収益」をどのように獲得するのか、その仕組み全体を指します。
事業を成り立たせる構造や手法であり、ドメインのような事業の範囲を定義する概念とは異なります。
要は、ドメインは企業や事業の「活動の場」を定義するのに対し、ビジネスモデルはその活動を成り立たせる「具体的な仕組み」を指しているということです。
目的も異なります。ドメインは持続的な成長のための事業領域の選択と定義が目的ですが、ビジネスモデルはその事業で収益を上げるための構造と手法が目的です。
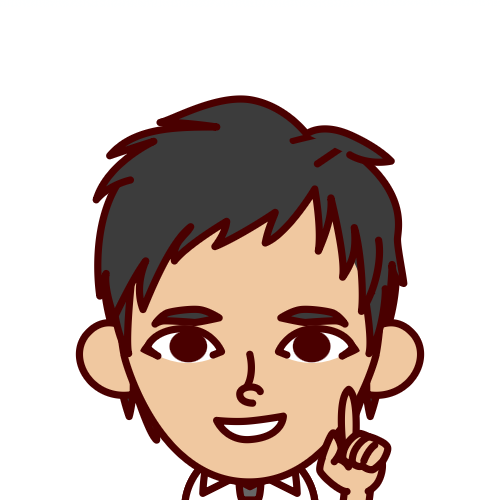
ビジネスモデルは単なる「儲け方」ではなく、「どうやって顧客と価値を交換し、持続的に関係を築くか」という事業の設計図、ということがポイントです
ビジネスモデルの主な構成要素
ビジネスモデルには明確な定義はなく、ざっくばらんに言うと「儲けるための仕組み」と言えます。
「誰に、何を、どのように、効果」は考えたほうがいいですが、それ以外のことは難しく捉える必要はありません。要は他社にマネされない仕組みがあればビジネスモデルになるのですから。
ただ、細かいことが気になってしまう方もいらっしゃると思うので、ここでビジネスモデルの構成要素を紹介します。
もちろん、ビジネスモデルの構成要素は絶対にこれ、というものはありません。
しかし、多くの人や企業が例として挙げているのは以下のようなものです。
顧客セグメント(誰に)
「どんな人・企業をターゲットにするか、誰にサービスを提供したいですか?」というものです。顧客層をビジネスモデルに入れるのいうことです。
例えば「組織文化を元気なものに変えたい中小企業の経営者と従業員に」とすればビジネスモデルの一部になります。
ターゲットを決める際は「サイコ、ジオ、デモ」を意識することと、顕在ニーズだけでなく潜在ニーズや本質的なニーズまで深掘りすることがコツです。
価値提案(何を)
顧客にとってどんな価値を提供するか、というものです。普通は顧客が困っていることやニーズを出しているもの、商品・サービスの強みになります。
例えば「ほめ達認定講師によるほめる組織文化への矯正コンサルティング」とすればビジネスモデルの一部になります。
価値提案をを考える際には、顧客にどのようなメリットや価値、便益をもたらせるかを考えてみることがポイントです。例えば「ほめる習慣をつける」とか「離職率を下げる」ですね。
自分が提供できる役務や商品・サービスを組み合わせるほどニッチになっていきます。
チャネル(どうやって届けるか)
商品やサービスをどの経路で届けるか(店舗、ECサイトなど)です。
これは僕の場合、かなり幅広いです。人脈・ネットワークが広いため、キーマンと数多く知り合っています(もちろん定期的連絡で関係性を深めています)。それは全国にありますし、オンラインでも全国どこのオフライン(対面)も可能です。
顧客との関係
顧客とどう関わり続けるかを示したもので、サポートや会員制度などが該当します。
これはプロモーション戦略の内容です。僕の場合はこれも得意です。顧客との定期的な個別連絡をしますし、伴走支援やコンサルティングではアフターフォローもできるからです。
収益の流れ(どうやって稼ぐか)
収益の得方(販売、サブスクリプション、広告など)のことで、価格戦略の内容です。
ニッチトップになり差別化が図れれば、模倣困難性が高まり、長期的な競争優位が可能です。顧客のほうから依頼がきて、交渉力も高くなります。結果、高単価の受注が可能です。
また、顧問契約を結んだ際はサブスクと言うか、定額での使い放題サービスは僕も考えています。ですが、税理士事務所のように月に●回の訪問で月額●万円という形が定番だと思います。
主要資源
ビジネスに必要な人材、技術、資産などを指します。
診断士はサービス業なので、経営資源は自分自身です。自分の事務所や専用の設備がないといけないわけではありません。資金もそこまで確保していなくてもいいですよね。
逆に技術、つまりノウハウや知識、スキルは常に鍛えておく必要があります。それが知識の定期メンテナンスと、毎年の中小企業白書の概要把握です。
主要活動
価値を提供するために必要な活動(製造、開発、営業など)です。
僕の場合、これは講師やコンサルティングですね。
営業は必要になるでしょうが、自分から無差別に営業を行うのではなく、評判や紹介などで顧客のほうから来て、それを僕が選別する形になるのが理想ですね。
パートナー
協力する企業や個人(外注先、提携企業など)のことです。
要は連携相手です。2次試験でも定番ですね。自分に不足するスキルは外部から補います。
人脈・ネットワークを構築しているなら、診断士仲間とのコラボ商品・サービスもアリですね。
それぞれが得意分野を担当していけば、一人でやるよりもさらに良いものになります。
僕はそのための土台として、1年目から人脈・ネットワークを広げています。
また、キューピット役として人や企業をつなげることもしていますので、その縁で連携相手の人や企業も探しやすくなっています。

今回はビジネスモデルについて見ていきました。
いよいよキャリア分析の内容が具体的になってきましたね。
今回もありがとうございました。