みなさん、こんにちは。
前回はビジネスモデルの教科書的な内容を見ていきましたが、今回も教科書的な内容です。ただ、前回よりは実務的な内容になっています。
それでは、今回もよろしくお願いします。
今回も教科書的なことなので眠くなりそうということで、眠りにつける寝台特急サンライズ瀬戸にしてみました。忘れがちですが、JR四国には寝台特急があるんですよね。

「何を」の本質
ドメインやビジネスモデルには「誰に、何を、どのように」というのがありましたね。
その「何を」についてです。
顧客の課題を解決するということは、現状とあるべき姿があるということです。現状をあるべき姿にもっていくことが「何を」の本質です。コーチングやほめ達研修などは「何を」に該当するが、それはあくまで「手段」に過ぎません。
以前もチラッと述べましたが、なぜ買うのか、なぜ「あなたから」買うのかについて、明確に答えられないと(このブログのように文字化できないと)ビジネスモデルとして成立しません。だからこそ、僕は四国キャリア分析合宿によってキャリア分析を徹底的に行い、ブログで報告することで文字にして明確に答えられるようにしています。

「効果」を考える
2次試験の事例Ⅱ(マーケティング)のクセがある方なら、「誰に、何を、どのように」までいったら、「効果」もないと気持ち悪いですよね。
顧客がそれを利用したときの結果が効果ではありますが、これだけでは終わりません。その結果をもたらしたことによるポジティブな感情も考えていきます。これがあるからリピーターになることや口コミによる新規顧客獲得があるのです。
効果を考える際は、顧客にどのようなメリットや価値、便益をもたらせるかを考えてみることがポイントです。
例えば「ほめる習慣をつける」とか「離職率を下げる」ですね。ありきたりの内容よりは、「ほめる習慣とポジティブな雰囲気造成業」などと差別化が図れる言い方にするといいです。
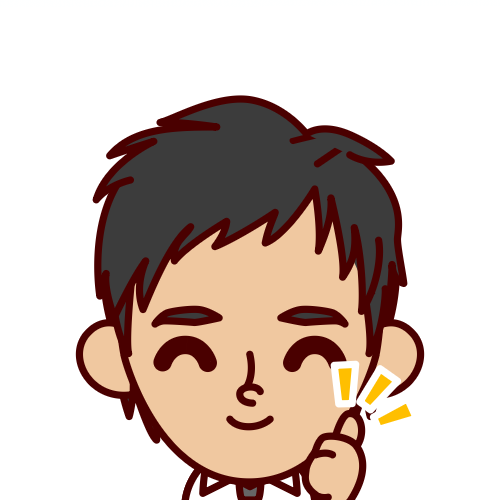
独自のドメインを見出し、有利なポジションを確保し、そこで自分だけの強みを発揮していくことでVRIOを満たし、競争優位が離れます
主観的な価値を意識する
これは前回見ましたね。
ニーズを解決して得られる結果や喜びに対して顧客はお金を払います。機能や特徴をアピールすることも大事ですが、結果や喜びをアピールし、顧客にイメージさせないと意味がありません。
機能や特徴はマネできても、結果や喜びはなかなかマネできないものです。これは感覚価値や観念価値など主観的な要素が影響しているためです。
・機能的価値:実用性・利便性など
・情緒的価値:心のつながり・感動など
・感覚価値:美しさ・心地よさなど五感に訴える価値
・観念価値:信念・理念・社会的意味に訴える価値
機能的価値では差別化は難しいため、情緒的価値、感覚価値、観念価値といった主観的なもので差別化を図ることになります。
見込み客の不安を解消する
説明やプランのわかりやすさ、明朗さは強烈な武器になります。顧客の不安を取ることができるためです。保険のようにごちゃごちゃしているプランはわかりにくくて敬遠されます。そのため、例えばコストを公開するのも手だと思います。
オーダーメイド型が中心
これは企業経営理論や運営管理でも「延期の原理」というものでやっていますね。
マーケティングのところでも見たように、昔は総花的な大量生産でしたが、今は顧客のニーズに合わせた双方向のビジネス、オーダーメイド型が傾向となっています。
アフターサービスや、ニーズによって提供できる要素を組み合わせて提供すること、顧客の満足度やLTVを高めることも先ほどの「ポジティブな感情」につながります。
契約を継続させる方法を考える
問題が解決・改善すると契約を打ち切られてしまうのがコンサルティングです。そのため、アフターサービスや定額利用などでつないでおく必要があります。もちろん満足度やロイヤルティなどLTV系の内容とも関わってきます。
このあたりは美容医療と同じビジネスモデルです。美容医療もいかに次の課題を顧客に出していくかが、契約を継続させるカギとなっています。
紹介の仕組みを作る
要は自分で営業をしなくても新規顧客が来るような仕組みを作ることです。
見込み客からのニーズがあるときに、顧客や他の診断士、関係者から一番に思い出される人になればOKです。
それができていると、自分自身がブランドになっている証拠です。
だからこそ、僕は「事例をたくさん知っている人、ほめる系のこと、メンタルヘルスのこと、交通系企業のこと、人の紹介が得意な人と言えばサトシ」と、たくさんの人が僕のことを思い浮かべてくれることを目指しています(これはすべてまとめてではなく、人によって異なる1〜2個です)。
リソースベースドビューを意識する
これは中小企業の戦略で出てきた内容です。中小企業は経営資源の質や量が不足しているので、強みを育成する、関連多角化で強みを多重利用する、選択と集中を図る、外部の専門性を頼る、双方向のコミュニケーションで個別対応を図ることなどが必要になります。
その状態でニーズに強みを適用させることで、VRIOを満たせ、差別化や持続的な競争優位が図れるというものです。
選択と集中を意識する
先ほどのリソースベースドビューの項目の1つにもありましたが、ターゲットでも提供するサービスでも何でもいいので、選択と集中を図ることが重要です。
これは言い方を変えると「何かを捨てる」ということです。これを決めることは同時に「やらないことを決めること」でもあります。診断士の2次試験で有名な岩崎邦彦先生の著書にもよく書かれている内容ですね。絞るだけで売上は上がります。
スーパーホテルが睡眠の質にこだわっているように、特定の要素に資源を集中し差別化を図る手も有効です。
事務的なことなど、見えない部分は効率化を図る一方、顧客の満足度に直結する見える部分は差別化を図ることをしています。
また、QBハウスがシャンプーや髭剃りをあえてやめてカットのみに専念したもののように、必要な要素をあえてカットする手も有効です。大手がそれをやろうとすると、シャンプーや髭剃りの機材がすべて無駄になってしまうからできないのです。
青山フラワーマーケットは個人のみをターゲットにして法人はターゲットから外しています。このようにターゲットをあえてカットする手も有効です。
戦う土俵を変える
これはレッドオーシャンとブルーオーシャンのことです。
わざわざレッドオーシャンだとわかっているところに飛び込む必要はないはずです。
例えば講師業なら対面だけでなく教材や資料のネット販売も行うほうがいいとされています。そして、ネット販売だとコストが少ないので価格も下げるのも定番です。
ですがこれはすでに多くの人がやっていてレッドオーシャンです。だからこそ、あえて日本全国どこでも行けるから対面のみにするという方針を出すことでブルーオーシャンになり、他の人との差別化を図ることができます。
今回はビジネスモデルを設定するにあたってのコツについて見ていきました。
今回もありがとうございました。