みなさん、こんにちは。
ここまで、僕が進むといいキャリアの路線のことを紹介してきました。
確認ですが、以下のものですね。
●中小企業の改善事例や白書解説
●ほめる系
●メンタルヘルス系
●交通系企業支援
●地域支援
●人の紹介(マッチング)
(一応、通常の講師業、執筆、思いつき段階のYouTuberとドリル教材作成もありますが、こちらは置いておきます)
今回はこれらの仕事をする際の僕の立ち位置といいますか、役割について述べさせていただきたいと思います。
それでは、今回もよろしくお願いします。
今回のサムネ画像は、高知県を走る観光列車の「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」です。「ものがたりシリーズ」の1つです。「ものがたりシリーズ」ではアテンダントが乗務していて、放送による案内は一方的な情報提供ですが、もちろん顧客の話を聞いて最適な情報を提供する双方向のコミュニケーションも行っています。
双方向の伴走者が前提
これは基本になるかと思います。もちろん講師として講義をする際は一方的な情報提供になってしまいますが、講師業でも受講者の相談や質問への対応は双方向で行います。
また、コンサルティングなら伴走支援です。こちらについてはコーチングでも最近は双方向、伴走者としての役割を意識されている方が増えているので、「双方向のコミュニケーション」としてはレッドオーシャンになります。
そのため、役割としてはコーチングのコーチに近いかもしれませんが、「アドバイスはしない、批判はしない」という意識をもつために僕はあえて「伴走者」という表現で捉えています。
ただ、コーチングのコーチも含めたレッドオーシャンの中で差別化や競争優位を図る必要があるのも確かです。それについては、例えばほめ達のスキルを活かすことや、診断士としてのきちんとした聴き方ができることにより、レッドオーシャンの中でも差別化や競争優位が図れ、結果的にブルーオーシャンであるほめる系、メンタルヘルス、交通系の講師業やコンサルティングにもっていくことも可能になるかと思います。

診断士としてのきちんとした聴き方については後日ご紹介します
盛り上げ役、モチベーター
これが言ってみればレッドオーシャンである双方向のコミュニケーションの中で差別化・競争優位につなげるための秘訣です。
双方向のコミュニケーションの中でほめ達スキルを使うことで、チームの盛り上げ役やモチベーターになることも可能です。
こちらは意識しなくても僕の場合、自然に行っています。なぜなら経営理念に「元気と勇気と希望を与える」があるからです。僕はこれができるからこそ、双方向のコミュニケーションを図っていて相手がやる気になってくれる、元気になってくれるのです。
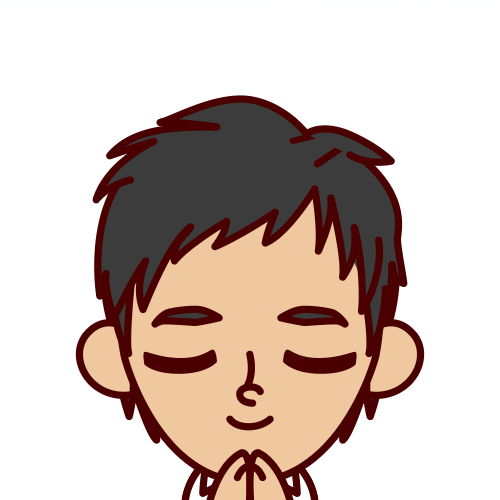
実際、このような趣旨の感想を結構いただいております
ファシリテーター
チームでやる場合、僕がメインになって先頭に出る必要があるとは限りません。他に素晴らしいメンバーがいるなら、その人たちが力を発揮できるように僕が指揮者やパス回し役になる手もあります。それがファシリテーターです。
こちらについては、次回の記事で詳しく見ていきます。イメージはディスカッションの司会者です。
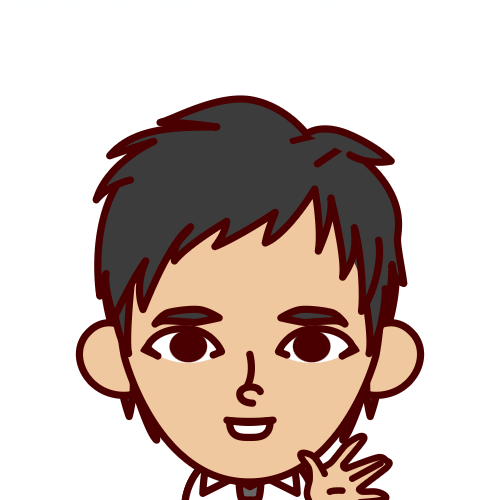
ファシリテーターの理想はABEMA Prime(AbemaNews)の司会進行をしている、テレビ朝日の平石アナウンサーですね
調整役、ハブとしての役割
こちらは人の紹介(マッチング)の仕事の場合ですね。僕の日本全国のネットワークや人脈の広さ、キューピット力を活かすことで、専門家どうしのハブになり、見返りとして対価や案件をもらうこともできると思います。

逆になくなったもの
今までは以下にある役割も意識していましたが、今回の四国キャリア分析合宿を機にこれらの役割は廃止し、双方向の伴走者、ファシリテーターとしての役割(人の紹介に関してはハブとしての役割)に絞ることにしました。
カウンセラー
僕は産業心理カウンセラー(産業カウンセラーの軽く取れる版)の資格をもっていますが、こちらは時代に合わなくなっていると思いました。
カウンセリングで役に立つのは精神疾患を抱えている人くらいです。もちろんメンタルヘルスの仕事でハラスメントの被害に遭った人に対してカウンセリングを行うことも可能ですが、カウンセリングはこちらの意見は言えません。実は一方向なのです。
一方向と言うと「こちらが一方的に話す」というイメージがありますが、「相手が一方的に話す」も一方向です。前者はアドバイザー、後者はカウンセラーのイメージです。
確かに、カウンセラーも質問を工夫することでコーチのようになることも可能ですが、相手の意見は全面肯定、こちらは意見を言わない、相手が気付くのを待つ、特定の結論に誘導するのは禁止ということがカウンセラーの前提になるため、余程腕の良いカウンセラーではないとただのイエスマンになってしまいます。
アドバイザー
アドバイザーについての役割は、受験経験や診断士の知識を活かすことでこちらもしていましたが、「アドバイスをする」となると上から目線になりやすく、双方向でやっているつもりでも、いつの間にか一方的に意見を押し付けるようになってしまいます。
どうしても「俺のこのやり方が正しいからこれに従え。それ以外は認めない」となってしまいやすく、そうなってしまうと謙虚さを失ってしまいます。
その点、双方向だと「私はこう思うけど、あなたの考えもいいと思う」のように、他の意見も認めやすくなります。これによって謙虚さを失わずに対応ができます。
今回は僕の役割について述べさせていただきました。
今回もありがとうございました。