みなさん、こんにちは。
今回は1〜3年目の方に向けた内容となります。
1〜3年目の診断士は新人・若手の期間なので、積極的なチャレンジや参加は大歓迎だし、会社の新入社員や若手社員のように失敗をしてもまだ許されます。ただし、その中でも留意点があります。今回はそちらについて見ていきます。
それでは、よろしくお願いします。

積極性についてはまだ別の機会で見ていきます
ゴールデン期間・シルバー期間
診断士の世界では、1年目は「ゴールデン期間、無敵期間」と言われています。マリオで言うスターをゲットしたようなものですね。
この時期は大学1年生のサークルのように、様々なところから勧誘や紹介があります。チヤホヤされます。知らないことを知らないと言っても全く問題ありませんし、失敗をしても許されます(責任は先輩が負ってくれます)。
2・3年目は「シルバー期間、準無敵期間」と言われます。効力は多少落ちますがある程度無敵の期間です。僕も今はこちらに属していることになります。
ただし、このゴールデン期間・シルバー期間に属する診断士も、気をつけないといけないことはあります。それが今回の記事のテーマです。
この3年間で診断士としての土台を築く
いくら「無敵・準無敵」と言っても、何の計画性もなく3年間を過ごせばいいわけではありません。
この3年間で診断士としての土台を築く必要があります。
本業を優先するあまり、診断士としての活路を見出す活動をしていないと、あっという間に3年間を終えてしまいます。4年目以降に慌てて動いても遅いです。そういう人が急にコミュニティに入っても他の診断士からは「え?今さらですか?ちゃんと計画を立てて診断士活動をすることができない人だな」と思われてしまいます。
例えて言うなら、大学のサークルに大学3年生が入るものですね。「そりゃ入ってもいいけどさぁ、普通は1年生でしょ?」となりますよね。「微妙な空気」になってしまいますし、他のメンバーも心理的に距離を置きやすく関係性も強化しにくくなります。
また、大企業勤務の方ほど本業で安定した収入があるため、診断士としての活動をするモチベーションが上がりにくい傾向があります。
しかしそういう方も2〜3年目になると、診断士の仕事へのコンプレックスと言いますか、診断士としての仕事をしていないことに焦りを感じてしまいます。
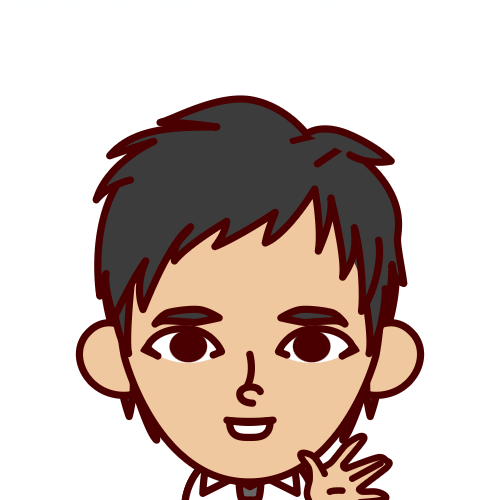
1年目(ゴールデン期間)で人脈と信用を築く、2・3年目(シルバー期間)でキャリアを加速させることがオススメです
1年目に種を蒔いてきた人脈と信用が2年目や3年目に活かされて開花します(僕も今それを実感しています)。だからこそ、診断士としての活動をしたいなら、特に1年目は積極的に行動していきましょう。この3年間でキャリアの土台を作りましょう。1に行動、2に行動、3・4も5も行動です。
なお、キャリアについてはこちらの記事をご覧ください。
「見習いなので」は顧客には無関係
コンビニや家電量販店など、小売店だとネームプレートに「トレーニング中」とか「研修中」と書いてある方がいると思います。これは見習いの店員だとわかりやすくしているためです。何かあれば先輩店員がサポートしてくれます。
病院でも研修医が担当する場合は「研修医なので」と説明します。これは医療ミスを防ぐためにも必要な説明で、いざとなれば経験と実力が豊富な指導医が対応してくれます。
診断士の世界でも、普通は見習いの診断士(1〜3年目の診断士)が仕事をする場合は先輩診断士が後ろに控えています。例えば補助金の仕事でも普通はチームでやらせて、その中には経験と実績がある先輩が入っています。そして1年目の人は負担の軽い補助的な仕事を担当するように仕事を割り当ててくれます。
しかし、だからと言って「見習いです」とクライアント(相手企業の社長や従業員)に言っても、クライアントからしたら関係ありません。ここが小売業の店員や研修医と異なるところで、士業の特性です。診断士なら1年目だろうが10年目だろうがクライアントは同じ扱いをします。
もちろん、「見習いです」を免罪符にしないようにしましょう。それが謙虚な態度にもなります。
生意気な態度は取らない
以前にも「1年目のペーペーが業界をわかっているようなことは言わない」と述べましたが、今回はそれの延長です。
いくら無敵とは言っても、先輩やクライアントに対して失礼があってはなりません。
診断士の先輩後輩は年齢ではなく診断士歴で決まります。つまり、年下でも診断士歴が上の人なら先輩になります
クライアントに対して失礼があってはならないのは当然ですよね。こちらの「診断士のコミュニケーション」の記事でも触れています。
問題は先輩に対してです。1年先輩の人だろうが、先輩に対して生意気なことを言ったり、「診断士としては後輩だけど俺のほうが年上だから年下のお前に言われる筋合いはない」みたいな態度を取ったりすると、当然のようにトラブルにつながります。ましてや実際にトラブルを起こしたら干されるのは目に見えています。
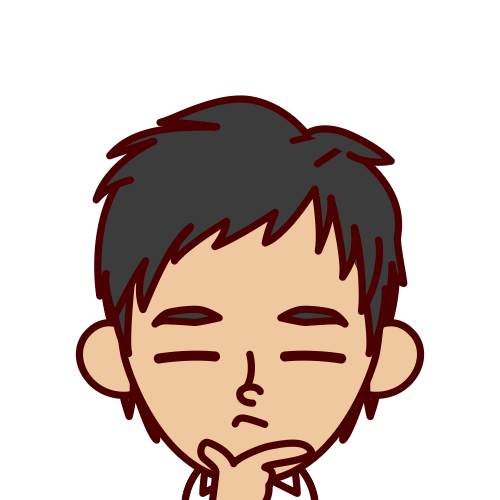
年配の人、プライドの高い人、正義感の強い人、善悪や優劣などタテの意識が強い人ほど注意が必要です
仮に自分の意見が100%正しい場合でも関係ありません。相手からしたら「先輩に楯突いてきた生意気な後輩」になってしまいます。表面上は「失礼しました。今後は気をつけます」などと大人の対応をしても、当然ですが関係性は崩壊します。二度と関わりをもってくれないでしょう。
また、周囲の人も「おぉ、良いこと言った!」とは思いません。「この人、先輩に対して失礼なことを言う奴だな。これじゃいつトラブルを起こすかわからないぞ」と思い警戒します。トラブルメーカーと仲良くなりたい人はいません。
今回は新人・若手診断士の留意点について見ていきました。
今回もありがとうございました。