みなさん、こんにちは。
前回は強みについて見ていきました。そして、相手に価値を提供する「真の強み」が重要であることも見ていきました。
今回はそんな「真の強み」をさらに有益なものにするために、「組み合わせる」ということをやっていきます。
それでは、よろしくお願いします。
真の強みを複数組み合わせる
サムネ画像でもありますが、「1本の矢はすぐ折れてしまうけど、3本束ねたら折れにくくなる」というのがありますよね。強みもまさにこれと同じです。1つだけなら差別化は難しくても、(真の)強みを複数組み合わせることで差別化が可能になります。
例えば僕の先輩では、ITスキルと発声のスキルを組み合わせることで活躍している人がいます。具体的には、「ITと発声のスキルを活かし、講師業やプレゼンを控える社会人に向けてzoomなどで発声の講演をする」という具合に活躍されています。
特にIT系、会計系、製造業の診断士は競合が多いため、強み1つだけではなかなか差別化は図れません。ご自身が属している(属していた)企業名では差別化は図りにくい印象です。差別化のためには複数の強みが必要になります。
サトシの真の強みを複数組み合わせる
前回も見ましたが、僕の真の強みは以下のものでした。
A.勉強・受験系:①診断士7科目の知識の質の高さ、②受験ノウハウ・経験+合格まで9年かかった苦労+診断士試験や様々な受験に関する知識やノウハウ
B.専門スキル系:①コーチングスキル(伴走支援スキル)+カウンセリングスキル、②中小企業白書横断的な知識+中小・小規模企業の事情把握+優良改善事例の知識、③鉄道や日本地理の知識・ノウハウ
C.コミュ力・メンタル系:①他の人とつなぎ合わせるキューピット力+新人メンバーの歓迎力、②双方向コミュ力(人と話す、人の話を聴く)+チームの盛り上げ役、良いムード、風通しの良さ+話しやすい雰囲気、親しみやすいオーラ、 感じの良さ(安心感・信頼・満足に繋がりやすい)+モチベーション向上(ほめ達、動く組織活性化)、③メンタル系(ポジティブ・強気・楽しい)
D.積極系:①日本全国に渡る人脈の広さ(ネットワーク力、取材の学校のネットワーク)、顔の広さ+発信力、②執筆などアウトプットのスピードの速さ
また、真の強みではないものの、「フットワークの軽さ」は活かすべき強みということでした。
では、差別化につなげるためにこの強みを複数組み合わせてみましょう。
例えば「日本全国に人脈がある」と「フットワークの軽さ」、「中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもつ」、「ほめ達」を組み合わせるとどうでしょうか?
・・・・・・・・・・
フットワークが軽いので、どこの中小企業や自治体にも行けますよね。そして、その地域の人脈を駆使することもできます。また、相談をしてきた相手に対してほめるスキルを使うことで、相手のモチベーションを上げて改善策に取り組みやすくさせることもできます。企業相手にほめる習慣による組織文化の変革に関する事業もできそうですよね。結果的に高品質の仕事ができ、相手も望んでいた成果が出やすくなります。
強みを組み合わせるほど競合の数が少なくなる
僕なら「中小企業診断士」以外にも上記のような真の強みがありました。そして、真の強みをいくつも組み合わせるほど差別化が図れるわけですが、それは真の強みを組み合わせるほど模倣困難性が高まり、競合が少なくなって唯一無二の存在になるからです。
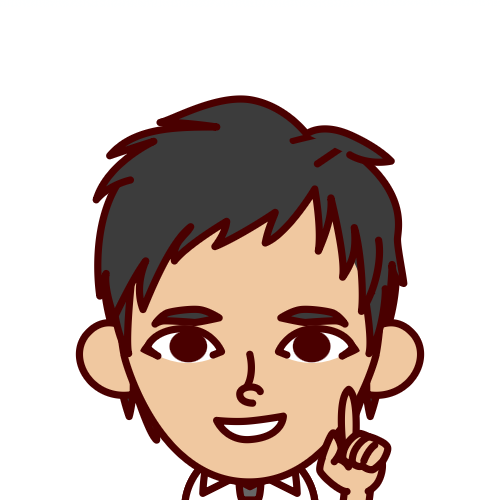
ここが診断士としてのキャリアのポイントになってきます
・中小企業診断士 →競合は数万人いる
↓
・フットワークが軽い中小企業診断士 →競合は1000人くらいになる
↓
・日本全国に人脈のあるフットワークが軽い中小企業診断士 →競合は100人くらいになる
↓
・日本全国に人脈のあるフットワークが軽い中小企業診断士で、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもつ →競合は20人くらいになる
↓
・日本全国に人脈がありフットワークが軽いほめ達の中小企業診断士で、中小企業や自治体の改善ネタを豊富にもつ →競合がいなくなる(唯一無二)
キャリア形成やブランド戦略では、この唯一無二の状態を目指す(確保する)ことが重要です。経済学で言う「独占」、企業経営理論で言う「ブルーオーシャン」ですね。ニッチャー戦略と言うか、ニッチ市場でのナンバーワンのイメージです。
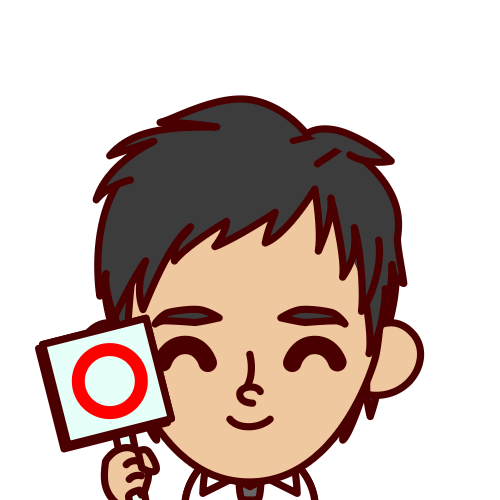
理想を言うと、こういうブルーオーシャンが3つあると盤石です
独占なら供給量を少なくでき、価格を上げることができますから、少ない負担で稼げるわけです。また、営業をしなくても勝手に顧客のほうから集まってきます。
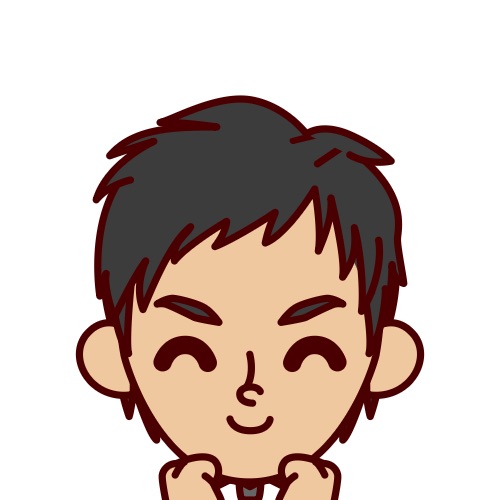
もちろん、独占は無理でも最低でも「寡占」の状態にはもっていきたいです
今回は、真の強みを複数組み合わせることについて見ていきました。
こうすると、真の強みの活用の路線が見えてきて、キャリア分析やブランド確立もしやすくなってきます。
ぜひこの記事を読んでいるみなさんも、ご自身でやってみてはいかがでしょうか。
今回もありがとうございました。