みなさん、こんにちは。
今回は居心地の良いコミュニティについて述べさせていただこうと思います。
それでは、今回もよろしくお願いします。
居心地の良いコミュニティほど長く居座ってしまう
専門的な取り組みや政策の研究会以外にも、人脈・ネットワーク構築や診断士としてのノウハウ習得がメインのコミュニティはどこの都道府県の診断士協会にも大なり小なりあると思います。これらのコミュニティは研究会に比べると目的が新人診断士にとってハードルの低いものであるため、居心地が良いことが多いです。
そして、こういうコミュニティは入れ替え制で入会してから1〜2年で強制退会(卒業)となるものが多いです。
情報受験生支援団体として診断士1年目の人がメンバーになれる一発合格道場やタキプロも1年間で卒業のコミュニティです。
こういう入れ替え制のコミュニティならいいのですが、中には永久に属することができるコミュニティもあります。なので、もしかするとみなさんの中には居心地がよくて何年もそのコミュニティに入っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そうすると、長期的に見たらいかがでしょうか?
10年や20年も前に合格した大先輩の診断士がコミュニティの「主」のように存在していて、毎年のように新人診断士を迎える形になります。そして「この大先輩に挨拶しなさい」と先輩に言われて挨拶をさせられます。
こんな光景、新人も先輩も見ていて楽しめますか?正直言って面倒ですよね。
仮にその大先輩の診断士が謙虚な方でも、10年も20年も診断士歴に差がある大先輩だと新人診断士からすると話しにくいです。これだと新人診断士は居心地が悪くなり、数ヶ月で離れていき、事実上の参入障壁になってしまいます。以前述べました、「新人診断士が入らなくていいコミュニティ」になってしまいます。
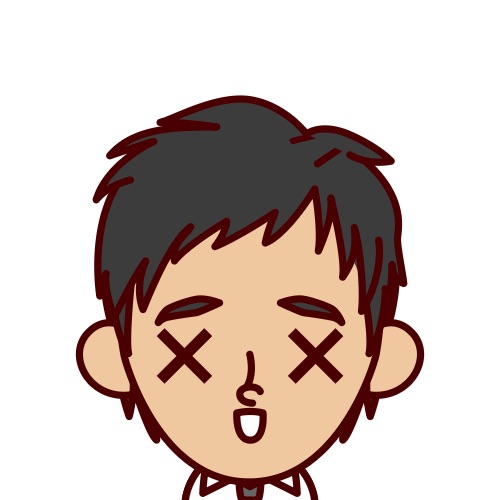
僕の感覚だと、5年以上離れている先輩だと新人は恐れ多くなって話しにくくなります
そうです。いつまでも「主」のように居続けることは、コミュニティの活性化の妨げになります。いわゆる「空気が読めない=KY」になってしまいます。居心地の良いコミュニティこそ、一定期間が経過したら空気を読んで卒業するべきです。「主」がいつまでも居心地の良いコミュニティにしがみついているのは、側から見ていると気持ち悪いだけです。
もちろん、その大先輩がコミュニティの最終責任者である場合やその人にしかできない業務がある場合は例外です。ただし、その場合でもその大先輩は表には出てこないようにする必要はあります。メンバーのみんなから信頼されている大先輩なら、滅多なことでは表には出てきません。
学校だってそうです。何年も学生をしている「主」のような先輩はいません。友達がたくさんできて、先生とも親しくなって学校生活に慣れてきて居心地が良くなったとしても、小学校なら6年、中学校や高校なら3年、大学なら4年で強制的に卒業ですからね。居心地が良いからといって自ら留年なんてしないですよね?
では、その「一定期間」とは具体的にどれくらいでしょうか?
後輩の話についていけなくなったら卒業
「一定期間」の一つが、後輩が多くなってきて話についていきにくくなったタイミングです。具体的な期間としては合格後3年ほどでしょうか(こちらについては後日、また詳しく見ていきます)。
永久に属することができるコミュニティだと、当たり前ですが毎年のように新人が入ってきます。そして、後輩がコミュニティに占める割合が徐々に高くなっていきます。
そんな中で、いかがでしょうか。後輩の話についていけないときってありませんでしょうか?
いくら自身が診断士とは言え、受験や合格の年度からはどんどん離れていきます。後輩がいても、自身が受験して合格した年との差はどんどん広がっていきます。自分が受験して合格した年と後輩が受験して合格した年の感覚は徐々に開いていきます。仮に僕のように知識の定期メンテナンスをして、診断士の1次試験と2次試験の問題が公表されたら毎年解くようなことをしていても、やはり実際の受験生や合格者とは勝手が違います。そのため、年を追うごとに後輩の話についていけなくなります。
それを認識したときが「卒業のタイミング」です。このタイミングを逃すと「空気の読めない主」になってしまいます。
いつまでも居心地の良いコミュニティにしがみついているのではなく、「若い者(後輩)が増えてきたところで老兵(先輩)は消え去る」が自然なのです。
若い診断士からすると、コミュニティにずっといる「主」は、(表向きの敬意は示しますが)正直なところウザいだけです。「この大先輩に挨拶しなさい」と先輩に言われて挨拶をすることや、先輩がその「主」に忖度する光景は、正直言って面倒なだけです。
診断士として自立できる目処がついたら卒業
もう一つのタイミングが、診断士の仕事が増えて診断士として自立できるようになった段階です。これも具体的には合格後3年ほどです。
診断士は基本的には合格してすぐに仕事がもらえるわけではありません。以前も述べたとおり、最初はボランティアベースで、徐々に小さな報酬の仕事がもらえるようになり、それを積み重ねることで中くらいの報酬の仕事がもらえ、それも積み重ねてようやく大きな報酬の仕事がもらえます。
この「中くらいの報酬の仕事を積み重ねる段階」になると、出費よりも報酬のほうが多くなり、損益分岐点売上高を超えます。つまり、この段階で診断士として自立できることができます。
このタイミングが「卒業のタイミング」です。もしくは先ほどの「後輩の話についていけなくなったとき」が卒業のタイミングです。

さらに言えば、大きな報酬の仕事をもらえるようになれば、1万円や2万円が当たり前のようなレベルになります。そんな中で会費1,000円のコミュニティのイベントに参加するのは、レベルが異なります。
一流企業の社長が会費4,000円の飲み会には参加しませんよね。やはり一流企業の社長なら会費40,000円の「食事会」に参加すると思います。
つまり、合格して2〜3年はそのような居心地の良いコミュニティにいてもいいですが、診断士の仕事が増えて診断士として自立できるようになった段階で自然と卒業していくことが、中小企業診断士としてのあるべき活動の姿であり、居心地の良いコミュニティの会員のあるべき姿のように思えます。
ちなみに、僕にもそういうコミュニティはあります。僕は「合格してから診断士として自立できるまでのコミュニティ」と捉えています。つまり、「診断士として自立できそうになった段階で、居心地の良いコミュニティは巣立っていく」と考えています。
もしかすると、このコミュニティの参加が診断士として唯一の活動もいう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方は診断士としての自分を保持するために何年もいてもいいのかもしれませんが、「主」のようになるのはやめたほうがいいかと思います。むしろ存在感を消し、後輩がどうしても助けてほしいときだけ助けるくらいでいいと思います。
居心地の良いコミュニティこそ、何年かしたら巣立っていく。年に1回の総会や同窓会的なもの、何年かに1回の記念イベント的なものなら参加してもいいかもしれませんが、通常の回は参加しない。もちろん後輩から何か相談があれば快く応じるけど自分から後輩に連絡はしないで見守るだけにする。仮にずっと居続けるとしても「主」のような存在にはならず存在感を消す。これが先輩診断士のあるべき姿だと思いました。
今回はちょっと哲学チックになってしまいましたね(笑)
今回もありがとうございました。