みなさん、こんにちは。
今回と次回は養成課程について見ていきます。次回の最後に、ちょっとした案内もあります(そのため、サムネ画像は中小企業基盤整備機構のロゴを引用いたしました)。
僕のブログはすでに診断士になっている方を基本的なターゲットにしていますが、受験生の方もいらっしゃると思います。
受験生の方なら、2次試験の代わりになるものとして養成課程があるのはご存知だと思います。ただ、どんなイメージで捉えていらっしゃるでしょうか?
今回と次回は、そんな養成課程のイメージを矯正する記事となっております。
それでは、よろしくお願いします。
養成課程=敗者復活戦の裏ルート??
僕は診断士試験に合格して7月に実務補習をやるまでは、養成課程は「どうしても診断士になりたい人がお金で診断士の資格を買う敗者復活戦のようなルート」と思っていました。
僕以外の診断士でもストレートや短期合格の方だと、「よくわからんけどお金を払って2次試験と実務補習のようなことをする裏ルート」というイメージかもしれません。
もしかすると、受験生もそのように捉えていらっしゃるかもしれません。当たり前ですが予備校では養成課程のことをポジティブに勧めることはありませんし、僕がいた一発合格道場やタキプロのような受験生支援団体も養成課程卒のメンバーはいません。正確に言うと養成課程卒の方もメンバーになることはできるのですが、やはり試験合格のためのコミュニティなので、養成課程卒の方は参加しにくいのが実状です。
おそらくですが、受験生が養成課程を受けるなら、
・勤務先が費用を出すので1次試験に合格したら行くように言われた
・2次試験を何度も受験しても合格できなかったから、最後の手段として行くことにした
・どうしても来年(今年)には診断士になっていないといけないから行くことにした
のどれかではないでしょうか?
それは養成課程に上記のような「敗者復活戦」とか「裏ルート」みたいなイメージがあるからです。そしてそれは、2次試験合格者を勝者と捉え、それを表ルート(正規のルート)と認識していることが根本にあります。
はい、今回の記事でそのイメージが変わります!
では、見ていきましょう。と言っても、今回の記事は途中までです。
敗者復活どころか即戦力
では、養成課程の方のスペックはどれくらいでしょうか?やはり、2次試験合格組より低いのでしょうか?
僕は診断士に合格してから実際に養成課程を卒業された方と話をしたり、一緒にコンサルの仕事をしたり、養成課程の講義や実習の風景を見せてもらったりしたことがあります。
そうしていくするうちに、「敗者復活戦の裏ルート」という思いは吹き飛びました。
具体的に、資料作成力、環境分析・改善策考案の力、実際の中小企業の肌感覚、コンサル経験などは試験組よりはるかに上でした。プロ野球で例えると、いきなり1軍で通用するルーキーのレベルです。
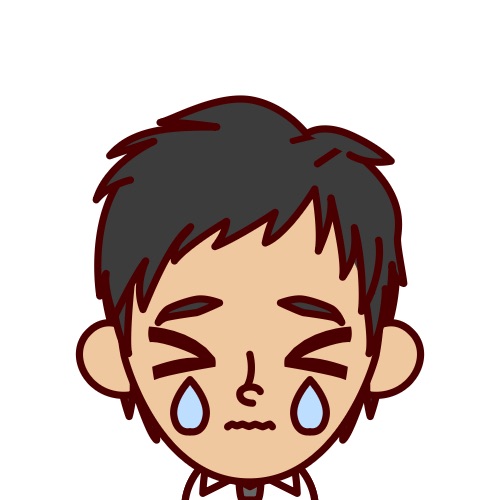
ということは、試験合格組は・・・通用するとは言えないのです
養成課程のカリキュラム
養成課程では講義(演習)と実習があります。演習と言うと答練のようなアウトプットのイメージがありますが、講義半分、ワーク半分のイメージだそうです。
大まかに分けると、講義は1次試験、実習は2次試験と実務補習に相当します。
①講義(演習)
講義では企業の問題点や改善策についてグループごとに議論することが多いです。僕も見学させてもらいましたが、かなり活発的に議論をしていました。
また、財務や流通、店舗経営、生産などの知識を深めていくこともあり、診断士の1次試験の各科目の知識をより実践的なレベルまで深掘りしていきます。
どうしても試験だと、1次にしても2次にしても、教科書的な内容が多く実践的な内容は避けられやすいです。しかし、養成課程だと実践的なレベルまで学ぶ(実習で実践する)ことができます。
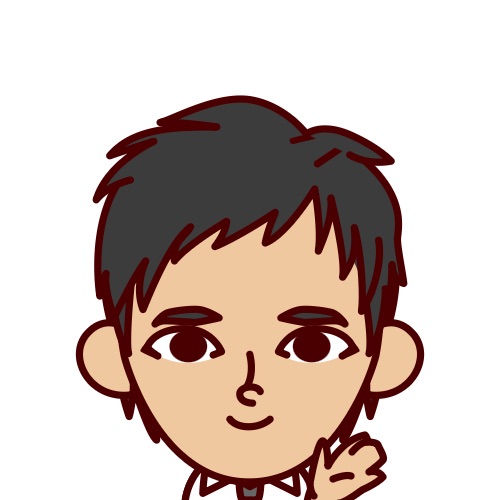
講義のイメージは1次試験の内容をよりリアルに近いものにしたものです
②実習
2次試験合格組だと、実務補習として3社(令和7年度からは2社)経験しますが、1社ごと期間は短いです。途中のインターバル期間を入れても2週間ほどです。
しかし、養成課程組は実務補習の位置付けである「実習」で5社経験します。また、1社あたり1ヶ月ほどかけます。さらに、実務補習ではそこまで重症ではない企業を相手にすることが多いですが、養成課程の実習で扱う企業は実務補習よりも厳しい状況下の企業であることが多く、改善策の内容も明日から実践できるレベルの具体的なものが求められます。なので、実務補習より求められている水準が高いです。
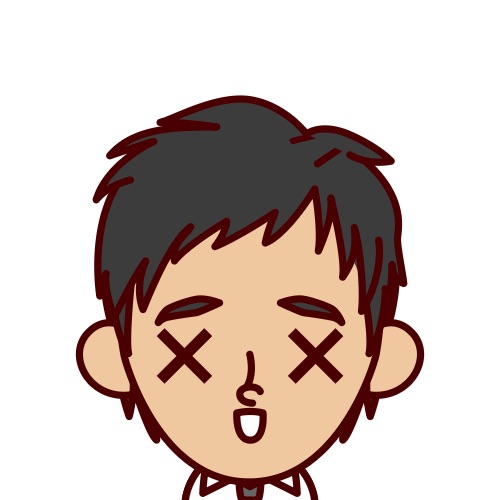
しかも、成績次第では途中退学もあるそうです。実際に僕も養成課程卒の方なら何人か脱落した人がいることを聞いています
実務補習をすると必ずぶち当たる壁が、大企業の理屈や机上の空論での改善策を提案してしまい、相手の経営者に断られることです。
企業の経営は教科書通りにはいきません。中小企業診断士として学んだ知識や理論がそのまま当てはまることはほとんどありません。教科書の知識や理論より「経営者に納得してもらい、こちらが提示したことをやってもらうこと」が重要なのですが、試験合格組はどうしてもここで壁にぶち当たります。
養成課程はこのあたりの対策もしっかりプログラムに入っているため、卒業生は「経営者にやってもらえること」を重視した改善策を提案してきます。
このように、養成課程では講義も実習も、診断士の1次試験、2次試験+実務補習よりも深いレベルまでやっています。しかも成績次第では途中で退学(戦力外通告)。
ということは・・・
先ほど、「2次試験合格が勝者の表ルートで、養成課程は敗者復活戦の裏ルートのイメージが受験生にはある」ということを述べましたが、この話を聞いていかがでしょうか?
講義も実習も、表ルートの2次試験合格組よりハイレベルなことをやって、(成績が悪い人は途中退学となり)卒業生はそのハイレベルの力をもって卒業します。
そう、養成課程卒の方は即戦力で診断士の世界に出てきます。
試験合格組(特に新人診断士の方)も、うかうかしていられなくなったのではないでしょうか?
今回は養成課程に関するイメージの矯正について見ていきました。養成課程の話は次回も続きます。
今回もありがとうございました。