みなさん、こんにちは。
前回は鉄道系YouTuberの特徴について見ていきました。
今回はその特徴から診断士として学べることをご紹介します。
それでは、今回もよろしくお願いします。
説明は短く簡潔に、メリハリをつける
これは前回の鉄道系YouTuberの特徴の①・⑦・⑧を踏まえた内容です。
例えば打ち合わせで説明しているとき、何の話をしているのかわからないくらいダラダラと話してしまうことはないでしょうか?zoomや貸会議室など時間制限があるのに1人で長々と説明してしまうことはありませんか?メリハリがなく要点がわかりにくい説明をして聞き手を眠らせていませんか?
診断士ならば、診断士どうしの打ち合わせにしても、クライアントとの打ち合わせやプレゼンにしても、説明は短く簡潔に、メリハリをつけて行うこと。これが鉄道系YouTuberから学べることです。
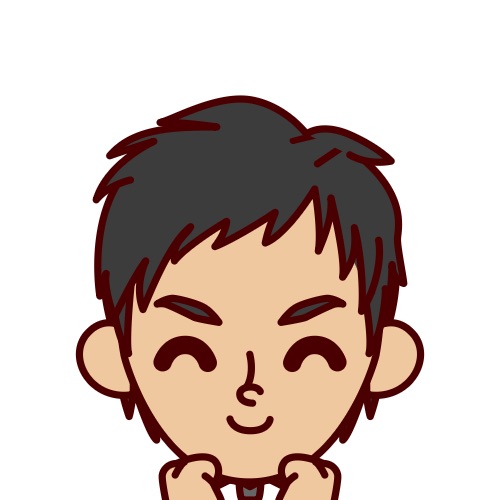
「短く簡潔に、メリハリをつけて」というのは、プレゼンの基本でもあります
ポジティブな言い方をする
これは前回の鉄道系YouTuberの特徴の②を踏まえた内容です。
やはり活躍する診断士になるために必要なのは「ポジティブ」ですよね。ネガティブに言うのはNGです。ましてや直接的な批判・否定はもっとNGですし、他人に悪口を言う形でもダメです。ポジティブについては耳にタコができるほど述べていますので、これくらいにしておこうと思います。
楽しく活動する
これは前回の鉄道系YouTuberの特徴の④・⑤を踏まえた内容です。
こちらも活躍する診断士になるための三大態度の1つですね。
「金のため、生活のため」が事情としてある方もいらっしゃると思いますが、やはりそこから悲壮感がある雰囲気がしていると、人脈・ネットワークや仕事につながりにくくなります。
活躍している診断士になるためには、ネタ半分でも独特の癖があってもいいので、楽しそうに活動している必要があります。
例えば僕は鉄道系診断士として、大井川鐵道に取材に行き、企業診断ニュースの記事を書かせていただきました。趣味と仕事の両立ができていて楽しかったです。
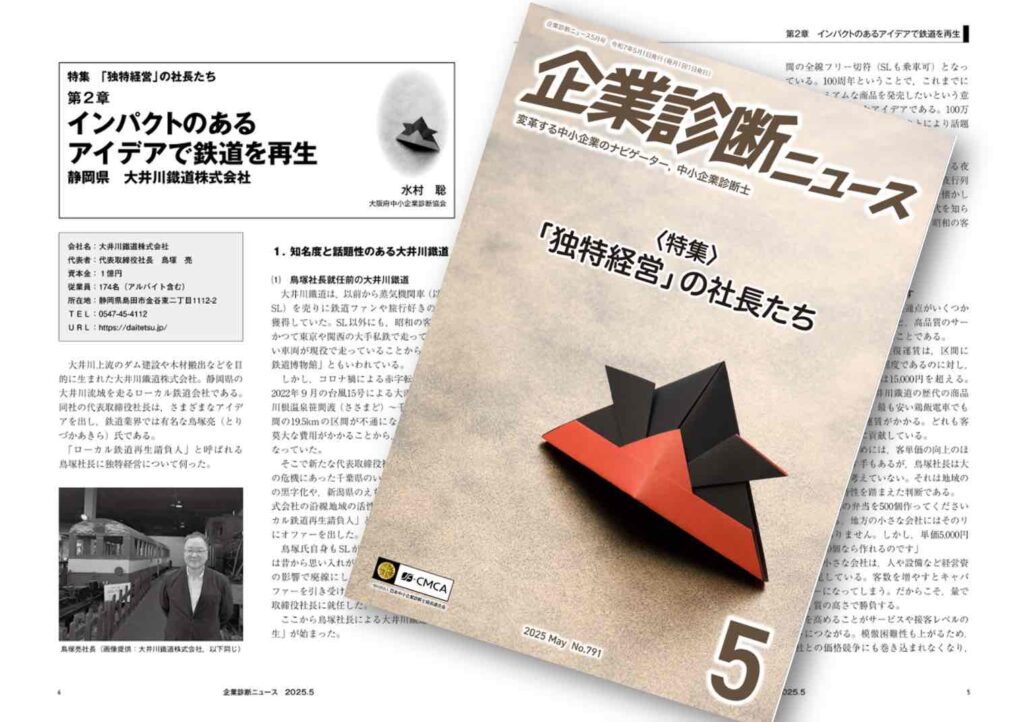
謙虚さ+相手への敬意などを忘れない
これは前回の鉄道系YouTuberの特徴の③を踏まえた内容です。
こちらも三大態度ですね。上から目線や感じの悪い話し方・態度は同じ診断士だけでなく、クライアントや様々な人の不快感を招きます。それだけ診断士の活動に不利になります。
また、謙虚さということは、相手への敬意なども忘れてはなりません。
問題を起こさない
これは前回の鉄道系YouTuberの特徴の⑥を踏まえた内容です。
これは当たり前ですよね。実際にトラブルを起こしていなくても、いつトラブルを起こすかわからないトラブルメーカーのように思われてしまうと、人脈・ネットワークは広がりませんし、仕事獲得もできません。そんな危ない人など顧客に対応させるわけにはいきませんし、他の診断士にも紹介したくないですよね。
実際に問題を起こしたら、同様の仕事は獲得できなくなります。例えば執筆の仕事で納期遅延を起こし、その人のために用意していたページを広告で埋める対応をした場合、今後の執筆案件は一切なくなります。
知名度のある人とつながる+学ぶ
これは前回の鉄道系YouTuberのZAKI(敬称略。以下同じ)の話を踏まえた内容です。
ZAKIは、最初はそこまで知名度はありませんでした。しかし、あるタイミングで知名度のある同業者である西園寺と連携しました。西園寺のサポート(動画編集や出演)に回ることで、西園寺の知名度と西園寺から吸収した面白い動画の作り方をもとに、チャンネル登録者数を大幅に増やし、鉄道系YouTuberとしてのランキングを上げています。
診断士もこのやり方を使えます。2次試験でも事例Ⅱでやりましたよね。知名度のあるところとは連携です。つまり、ご自身にまだ知名度がないなら、知名度のある診断士(著書を出している、何回もセミナーをやっている人など)とつながりましょう。イベントやセミナーで知り合うことができたら、Facebookで友達申請しましょう(余程のことがない限りは承認してくれます)。
そして、その診断士のFacebookの投稿にコメントをしたり、メッセンジャーで個別にメッセージを送ることにより、名前を覚えてもらえ、応援してもらいやすくなります。
それにより、例えば著書製作のメンバーやセミナーのサポートメンバーに選ばれるようになります。また、知名度のある診断士から診断士としてのスキルや他の診断士との付き合い方、コミュニケーションの方法などを学ぶことができるようにもなります。
以上、鉄道系YouTuberから診断士として学べることを見ていきました。定量的な数値や順位として鉄道系YouTuberのデータに反映されているからこそ、「ポジティブ・楽しい・謙虚」の三大態度を満たすことや、問題を起こさないこと、必要に応じて連携することなどへの説得力が出てくると思います。
今回もありがとうございました。