みなさん、こんにちは。
前回まででほめることの効果を見て、そんな効果のあるほめ達は決して怪しい宗教ではないこと、因果関係で説明できないことを言われたら無視していいことをお伝えしました。
そして、ほめ達検定の各級の内容を見ていきました。
今回はそれを聞いて安心してほめ達検定の受験やほめる能力を鍛えることを考えていらっしゃる方に対し、そのやり方をお伝えします。
それでは、今回もよろしくお願いします。
観察力
ほめ達になってほめる能力を鍛えていくためには、まずは観察力を鍛える必要があります。
ほめ達は目の前の人・モノ・出来事について「価値」を発見し、それを伝えることをしていくわけですが、価値を発見できなければ話になりません。価値を発見するためには、観察力を鍛える必要があります。
目の前にいる人について、外見、内面、身の回りのもの、仕草などを観察してみましょう。誰にでも必ず「ほめるところ=価値」があります。どんなにファッションが奇抜な人でも、顔が怖そうな人でも、ヤンキーのような態度を取っている方でも、迷惑行為をしている人でも、例外なく「価値」はあります。
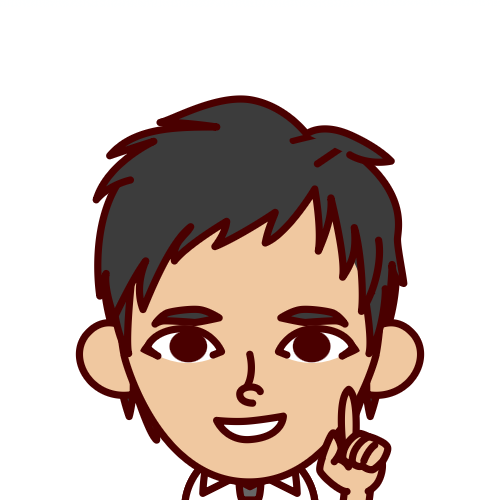
「こいつはほめるところがない」と決めつけるのではなく、視野を広くもってみましょう
モノや出来事についても、ポジティブな面やメリット、貢献できることなどを観察して見つけてみましょう。
変換力
この変換力がほめ達としての力に大きく影響します。
変換は、視点を変える「リフレーミング」というやつです。ネガティブなことをポジティブなことに変えるスキルですね。
人間は防衛本能があるため、放っておくとネガティブなことに目がいきがちです。解釈もネガティブなことが優先されやすいです。そして、ネガティブな解釈で自分に都合の良いようにラベル貼りをしてしまいます。そのため、放っておいたらネガティブな解釈が出てきてどんどん進んでしまいます。そしてネガティブ思考はアリ地獄の性質があってどんどん重症化します。
だからこそ、ネガティブな解釈が出る前にリフレーミングによってポジティブな解釈や見方に変換する能力が必要とされるのです。それがあるのが「ほめ達」です。
例えば「ケチ」とか「落ち着きがない」という短所も、何もしないとネガティブなことしか思い浮かばないですよね。そこで、リフレーミング(言い方の矯正)によって「いざというときにお金を大量に使える」や「周囲の様々なことに気がつく」など、ポジティブな表現に変換していきます。そうすることで長所になります。
ほめ達はこの「変換」のトレーニングを多く積んでいて、変換のスキルが高いのです。
この変換については、次の記事でさらに詳しく見ていきます。
伝える力
最後は伝える力です。いくらポジティブな価値を発見(変換)しても、実際に相手に伝わらないと響きません。また、伝える言い方が悪いと相手に効果的に響きません。
もちろんですが、ポジティブな言い方で伝える必要があります。感謝や労をねぎらう言葉も発していく必要があります。その点、ほめ達はポジティブで楽しい言い方をしていきます。また、対応も謙虚ですし、感謝や労をねぎらう言葉もこまめに相手に伝えています。
逆に、ネガティブな言い方はNGです。例えば、いわゆる「3D」と言われる「でも、だって、どうせ」や、「ただ、けど、いや、しかし」を話の最初につけるのもやめていきましょう。「だって」と「どうせ」はさすがにないとしても、それ以外のことはやっている方が多いのではないでしょうか?
あと、「まぁ」は上から目線につながるので、こちらもやめていきましょう。
ほめフレーズを染み込ませる
ほめ達の記事になってから、各回の最後に「今日のほめフレーズ」というコーナーを設けていることにお気づきでしょうか?
伝える力を高めるために、各回で紹介している「今日のほめフレーズ」を染み込ませましょう。
ほめフレーズと言えば「すごい、さすが、素晴らしい」を挙げる方が多いですが、それ以外のフレーズも口癖になるまで体に染み込ませていきましょう。ほめフレーズは「覚える」ではなく、「何度も使って口癖になるまで染み込ませる」ことが重要です。
意識してほめ続ければ、やがてそれが体に染み付いて習慣になります。無理している雰囲気がある人よりも自然体でできる人のほうが、相手への印象は良くなります。
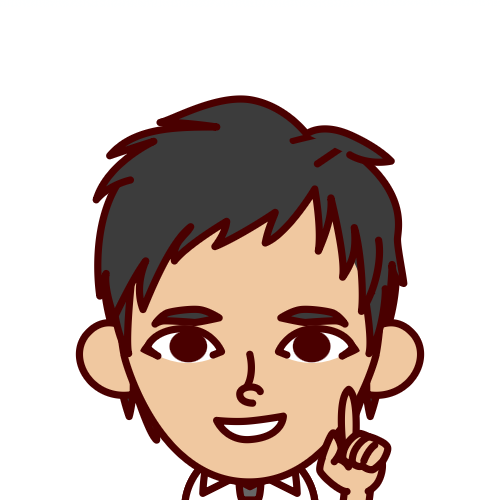
ほめ達はほめ癖がついているので自然体でスラスラとほめることができます
ほめ癖は3ヶ月くらい意識してやっていくとついてきます。今から3ヶ月間、ほめることを意識してみませんか?
《今日のほめフレーズ》
(いつもながら)最高!
今回はほめる能力の鍛え方について見ていきました。次回はその中の変換に関する内容をより詳しく見ていきます。
今回もありがとうございました。